日本旅行で家族と食事体験を深め心の豊かさや自己発見を促す
- 旅先ごとに2種類以上の地元料理を家族全員で味わう機会を作る。
地域文化や食材背景への理解が高まり、共通体験として会話が自然に増える。
- 毎日1回はスマホなしで食卓を囲み、20分以上ゆっくりと家族と向き合って食べる。
心身のリラックス効果だけでなく、安心感や親密度が育ち家庭内コミュニケーションも円滑になる。
- 訪問した土地ごとの朝食・一汁三菜スタイルなど伝統的な和食法を最低1回実践する。
自分の好みや生活リズムに気づくきっかけになり、新しい視点から日常にも活かせるヒントが得られる。
- (祖父母世代も同行なら)昔ながらの習慣や思い出話をひとつ聞いてみて記録する。
世代間交流によって心への影響・価値観変化が感じ取れ、自身の日々にも温かな余韻が残る。
日本で再訪を重ねて新たな自分に出会う方法
休みになるたび、どこかに出かけては、気がつけば胸の奥に小さな傷を増やして帰ってくるんです。まあ、どうでもよさそうに聞こえるかもしれないし、実際それで済む話なんだけど……でも初めて日本を旅した去年は本当に、もう立ち直れないくらい打撃を受けた感じでした。正直、日本という場所について全然分からないことだらけだと思うんですよ。だけど、とにかく妙に惹きつけられてしまう——説明できない不思議な力がある国なんでしょうね。いや、本当は「まだ」分からないだけなのかな。それ自体がずっと頭の片隅にあって、何度も考えてしまいます。「また行かなきゃ」とふと思うときがあります。一度じゃ絶対足りない国って世の中にはあるものです。
飛行機でクアラルンプールに戻る道すがら、「一体あと何回ここへ来れば、この胸の渇きは消えるのか?」——そんな問いが、自分でもバカみたいにつぶやいてました。変ですよね。でも、その一度だけの旅なのに、自分自身とか世界への向き合い方まで根底から揺さぶられた気がするんです。本筋……ああいや、ごめんなさい脱線しましたけど、本当に価値観まで書き換えられました。
ところで今は兄が家族連れて再び日本滞在中です。最初は新婚夫婦として訪問してたんですが、今回は四歳になった姪も一緒みたい。どうやら千葉県の東京ディズニーランド、それと大阪のスーパー・ニンテンドー・ワールドにも行くらしい。うーん……そこ正直まったく刺さらないな、自分には(笑)。私の場合、それより昔ながらのもの──例えば美術工芸館とか、公園巡りや現地ご飯を楽しむこと──そっち系ばっか考えちゃいますね。
温泉、しかも誰にも邪魔されず独占できるところなら文句なし。それこそ夢見た理想郷になる気しかしません。ま、いいか。
飛行機でクアラルンプールに戻る道すがら、「一体あと何回ここへ来れば、この胸の渇きは消えるのか?」——そんな問いが、自分でもバカみたいにつぶやいてました。変ですよね。でも、その一度だけの旅なのに、自分自身とか世界への向き合い方まで根底から揺さぶられた気がするんです。本筋……ああいや、ごめんなさい脱線しましたけど、本当に価値観まで書き換えられました。
ところで今は兄が家族連れて再び日本滞在中です。最初は新婚夫婦として訪問してたんですが、今回は四歳になった姪も一緒みたい。どうやら千葉県の東京ディズニーランド、それと大阪のスーパー・ニンテンドー・ワールドにも行くらしい。うーん……そこ正直まったく刺さらないな、自分には(笑)。私の場合、それより昔ながらのもの──例えば美術工芸館とか、公園巡りや現地ご飯を楽しむこと──そっち系ばっか考えちゃいますね。
温泉、しかも誰にも邪魔されず独占できるところなら文句なし。それこそ夢見た理想郷になる気しかしません。ま、いいか。
家族旅行のすれ違いと和食から学ぶバランスの大切さ
家族が集まる場面って、まあ、それぞれ違う人生の物語を抱えてくるので、正直ややこしい。四人兄弟姉妹が全員異なる趣味関心で、そのせいもあって「じゃあ今年は家族旅行…?」なんて話になれば、そりゃ計画するだけで頭が痛くなったりする。なんなら、一人は基本的に外出自体イヤがるから、もう言葉少なにため息しか出ない感じだ。
で、自分について言えば……「お前、高価志向だろ」とか、「めんどくさい旅人だよね」なんて陰口(いや正直な意見?)を耳にしたこともある。でもね、これは妙に釈然としない。「高価なもの」を求めてるわけじゃなくて、本当はバランスとか雰囲気への固執みたいなのが強いだけでさ――えっと、“慎重”とか“入念”みたいな単語のほうが近いと思う。本当にそういう傾向だから困っちゃう。
ちょうど、日本の和食で大切と言われる一汁三菜――ほら、「一つの汁と三種のおかず」という組合せに似た発想かもしれない。和食(washoku)は日本独特の伝統料理という以上に、その素材選び・調理法、それに宿った文化的意味までひっくるめた概念でもある。一方、一汁三菜(ichiju-sansai)はその中でもより具体的な構成になっていて、日本では食卓の基本フォーマット的扱いなんだよね。
うちの兄弟姉妹たちは別段考えすぎず、ファストフード片手ですぐ出発できちゃうようなタイプだったりする。一方自分の場合はと言うと、新鮮さ、多様性、風味、それと全体バランス――こういった和食の本質ともいえる四観点への想い入れがある。不思議だけど、大事なんだよね。
日本暮らししてた頃には、もちろん味噌や抹茶、有機食品など―本来のおいしさというものにも時折心底幸せを感じたりした。でも実際には、受け入れるには骨が折れる現実ともぶつかったことも忘れられない。それは結局、自分がどんなに馴染もうとしても幾つかの文化要素だけは結局“外来”感覚で残ってしまう、という哀しさだったと思う。ため息混じりになるけど、日本ならではの発酵とか鮮度追求への凝りよう、その執着にもいつも圧倒されっぱなしだった。
で、自分について言えば……「お前、高価志向だろ」とか、「めんどくさい旅人だよね」なんて陰口(いや正直な意見?)を耳にしたこともある。でもね、これは妙に釈然としない。「高価なもの」を求めてるわけじゃなくて、本当はバランスとか雰囲気への固執みたいなのが強いだけでさ――えっと、“慎重”とか“入念”みたいな単語のほうが近いと思う。本当にそういう傾向だから困っちゃう。
ちょうど、日本の和食で大切と言われる一汁三菜――ほら、「一つの汁と三種のおかず」という組合せに似た発想かもしれない。和食(washoku)は日本独特の伝統料理という以上に、その素材選び・調理法、それに宿った文化的意味までひっくるめた概念でもある。一方、一汁三菜(ichiju-sansai)はその中でもより具体的な構成になっていて、日本では食卓の基本フォーマット的扱いなんだよね。
うちの兄弟姉妹たちは別段考えすぎず、ファストフード片手ですぐ出発できちゃうようなタイプだったりする。一方自分の場合はと言うと、新鮮さ、多様性、風味、それと全体バランス――こういった和食の本質ともいえる四観点への想い入れがある。不思議だけど、大事なんだよね。
日本暮らししてた頃には、もちろん味噌や抹茶、有機食品など―本来のおいしさというものにも時折心底幸せを感じたりした。でも実際には、受け入れるには骨が折れる現実ともぶつかったことも忘れられない。それは結局、自分がどんなに馴染もうとしても幾つかの文化要素だけは結局“外来”感覚で残ってしまう、という哀しさだったと思う。ため息混じりになるけど、日本ならではの発酵とか鮮度追求への凝りよう、その執着にもいつも圧倒されっぱなしだった。

和食・一汁三菜がもたらす自己認識の変化を実感しよう
どうも、刺身の独特な生臭さって昔から苦手なんだよね。いや、好きな人も多いけど、ああいう匂いを感じると妙に寄生虫とか浮かんでしまう——ま、神経質過ぎるだけか。でも、それとは対照的に汁物になると別。本当に吸い寄せられてしまう自分がいる。雨の日だろうが晴天だろうが、とりあえず温度とか季節も無関係に、汁や吸い物はそっと心を包み込んでくれる気がする。一種の“慰藉の糧”かな。
穏やかな潮騒を孕む昆布――乾いた海藻のシートみたいなもの――あれから丁寧に引き出した出汁には、不思議な安堵感というか健やかな安心を覚える。ちょっと大袈裟?でも日本へ行った時、自分でも初めて「食べ方の背景にある思想」みたいなものをわかった気がして。不意に新しい土地へ放り込まれた異邦人として、自分がどれほどその環境と馴染まない存在だったか、改めて思い知らされたし。
私はしばしば「偏食家」扱いされることがあるけど、それもちょっと違う話かも。本当は極端な好き嫌いじゃなく、「調和」と「均衡」を考えてしまう癖みたいなのだ。……いや、それも結局亡き祖母の影響なんだよね。[1]台所で長々と一緒に立って、小さな動作ひとつまで付き合わされ(と言ってしまった)、下準備から細やかな盛り付けまで何時間も一緒にこなし続けた。
祖母は、ごく静謐だけど狂いなく正確で、じゃが芋一個にも繊細なくらい集中し、人参だって粒ぞろいになるように切り揃えたりした。「味付け」に使うものも合成の旨味調味料(MSG)には一切頼らず、本当に適度で絶妙なバランスのみ厳格。そして手抜きを見せない人だった。ただそれって単なる几帳面さというより、「素材への敬意」と「待つ力」、言葉になりきれない直観力みたいなものが自然と滲んでいた気がする。
彼女の料理哲学——それから祖父による「食事時刻絶対厳守」という謎ルール、このふたつによって、「食」は自分の中では半分瞑想的な時間になった。口へ入れるものひとつひとつ全部意味があり、一緒に囲む相手との瞬間にも確実に意味が乗る。不思議なんだけど、その静寂とか上質なしゃべりこそ本質とも呼びたくなる。つまり…日本料理にも深く通じているような“由来への眼差し”——単なる栄養摂取以上の何か、大事される理由。それごとなぜだか今、とても愛おしく感じている。
穏やかな潮騒を孕む昆布――乾いた海藻のシートみたいなもの――あれから丁寧に引き出した出汁には、不思議な安堵感というか健やかな安心を覚える。ちょっと大袈裟?でも日本へ行った時、自分でも初めて「食べ方の背景にある思想」みたいなものをわかった気がして。不意に新しい土地へ放り込まれた異邦人として、自分がどれほどその環境と馴染まない存在だったか、改めて思い知らされたし。
私はしばしば「偏食家」扱いされることがあるけど、それもちょっと違う話かも。本当は極端な好き嫌いじゃなく、「調和」と「均衡」を考えてしまう癖みたいなのだ。……いや、それも結局亡き祖母の影響なんだよね。[1]台所で長々と一緒に立って、小さな動作ひとつまで付き合わされ(と言ってしまった)、下準備から細やかな盛り付けまで何時間も一緒にこなし続けた。
祖母は、ごく静謐だけど狂いなく正確で、じゃが芋一個にも繊細なくらい集中し、人参だって粒ぞろいになるように切り揃えたりした。「味付け」に使うものも合成の旨味調味料(MSG)には一切頼らず、本当に適度で絶妙なバランスのみ厳格。そして手抜きを見せない人だった。ただそれって単なる几帳面さというより、「素材への敬意」と「待つ力」、言葉になりきれない直観力みたいなものが自然と滲んでいた気がする。
彼女の料理哲学——それから祖父による「食事時刻絶対厳守」という謎ルール、このふたつによって、「食」は自分の中では半分瞑想的な時間になった。口へ入れるものひとつひとつ全部意味があり、一緒に囲む相手との瞬間にも確実に意味が乗る。不思議なんだけど、その静寂とか上質なしゃべりこそ本質とも呼びたくなる。つまり…日本料理にも深く通じているような“由来への眼差し”——単なる栄養摂取以上の何か、大事される理由。それごとなぜだか今、とても愛おしく感じている。
味わいだけでなく、祖父母の食卓習慣が生む心への影響に触れる
一口食べるたびに、「これ、どこから来たんだろう」と無意識につぶやきつつ、田畑と人の手が刻んだ犠牲へもふと想いを巡らせていた気がする。ぼんやりそんなこと考えながら、日本で初めて味噌汁を口にした日の記憶は消えない。それは驚くほどぬくもりに満ちていて、胸の奥まで何か柔らかなものが沁みてきたような…。ま、いいか。あの瞬間、不意に祖母の穏やかな面影と、祖父と並んで過ごした淡い記憶までよみがえる始末。その発酵香る味噌は塩分がしっかりしているわりに優しい旨味を放っており、マレーシアで慣れ親しんだ類似のものとは趣きが違った。不器用なくせになぜか熱心に磁器の椀とか漆塗りのお盆、それから炊き立てご飯――全部新しい顔で、自分には判別し切れずつい目を凝らしてしまう。けれどまあ…表向きは一様でも、一点一点微細な個性を感じ取れる余地もあり、そのぶん「このひと匙、この箸づかいが最後かも」と思って特別慎重に堪能した覚えがある。
訪問先では、不思議なほど同じ類いの質問攻勢。「フグ食べました?」「和牛はいかがです?」「神戸牛、ご存じですよね?」とか。「ウナギ? ウミガメも良いですよ」「ウニ試しました?」「それともクジラ肉とか馬刺し、とか?」「築地でマグロ挑戦済みです?」など──こういう豪勢さに圧倒されそうになる自分もいる。実際、その場面その舌だけじゃ正直到底受け止めきれなかった感覚もあるし、返答にも困惑したっけ。
訪問先では、不思議なほど同じ類いの質問攻勢。「フグ食べました?」「和牛はいかがです?」「神戸牛、ご存じですよね?」とか。「ウナギ? ウミガメも良いですよ」「ウニ試しました?」「それともクジラ肉とか馬刺し、とか?」「築地でマグロ挑戦済みです?」など──こういう豪勢さに圧倒されそうになる自分もいる。実際、その場面その舌だけじゃ正直到底受け止めきれなかった感覚もあるし、返答にも困惑したっけ。
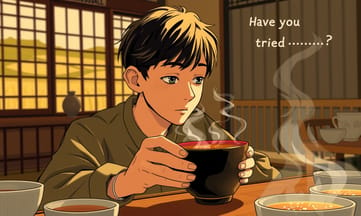
産地や食材の背景を知りながら日本各地の料理体験を楽しむには
本音を言ってしまうと、自分はいくら数えても足りないほどの失敗を重ねてきたんですよ。そういえば、生馬肉の前では結局食べる勇気がどうしても湧かなかったし、亀入り茶碗蒸しを前にただ呆然と箸が進まず、「天ぷらのフグ」を目前にした瞬間などは脳裏で死神が囁くような、不思議な寒さに包まれて震えていたっけ。新鮮とはいえ得体の知れないまぐろ刺身には、その独特な食感を前にして右往左往してしまったし――皆が「これぞ最高!」と言って憚らないものなのに、自分だけ好きになれなくて複雑だった。それじゃ、永遠によそ者のままということ?などとうっかり自問する瞬間もあって……いや、何だか面倒くさいですね。 旅から得たものは単なる“異文化理解”なんてもので語れなくて、本当に身を持って染み込む境界――自分は踏み越えられる限界がある、と痛感させる類いの経験だったんです。他国への淡い憧れや学び、それっぽい仕草すら試したとしても、結局越えられぬ壁ばかり残ることになる。実際向き合っていた敵は料理そのものではなく、多分「賞賛」と「所属」が容易には一致し得ない現実だった、と今さら思います。 皿上の馬一頭分、命が供されている事実ばかり目について仕方なかったとか、町一番と名高い新鮮なまぐろ刺身でさえ素直に美味しいと思う余裕が最後まで持てず……なんかダメですね、私。本当心底からおいしい、と感じたものと言えば、ごく普通に毎朝すすった味噌汁とか日々のお漬物、それからなぜだか蒸し蟹くらいで。それ以外には舌がどうにも追いつかなかったというべきでしょう。まあ、自分自身未熟なんだろうなあと小さく肩を落とすしかありませんでしたよ。でも、まあ……しょうがないか。
異文化への挑戦や失敗が本当の受け入れと繋がる瞬間を発見する
抹茶とか、ほうじ茶が当たり前みたいに並ぶ日々、その中でなぜかコーヒーを強烈に飲みたくなる瞬間があった。…ま、よくある話かな。どれも小さめのカップで差し出されるんだよね。不満ではないけど、なんというか手持ち無沙汰になる感じ。気づいたらStarbucksの自販機の前に立っていて、10 ozのカップが手元にきた時は妙な高揚感すらあった。そもそもマレーシアじゃ正直Starbucks避けてた方なのに、この矛盾には苦笑いするしかなくてさ。
日本――この国だと「食べる」という行為は、ただ体を養うだけのものじゃ全然ない気がする。ただ味わうだけじゃなく、その背後や由緒?大切されている雰囲気、やっぱり独特だな、と。一口ごとになんとなく産地や土、それを生む人の努力……静かな感謝が自分にも芽生えるような。「心して食事を」と昔祖母から何度も言われたっけ。その考えはいまだに離れない。「敬意」なんて言葉、自分でも使っておいて少し照れるけど。でもなあ、日本という場では、自分はいまだ訪問者のままでいるためだけにここに居るような錯覚を起こす瞬間がある。それって、おかしい?異文化への憧れって結局そういう不思議さと裏腹なのかもしれない。
本当に溶け込むってどういうことなんだろう。全部自分の物差しで測れるはずもなく、「触れていい場所」と「永遠に遠巻きでしか見られない部分」を見極め続ける作業、それが"没入"なのかも…。植物学ほど想定外だった発見は他になかったと言える。神奈川県足柄下郡、新仙峡庭園の日は微妙な曇天でさ、着ていたジャケットのファスナー喉元まで上げていたっけ。不意に浮かぶ——マレーシアなら多分布団にもぐりこんで過ごしてたかなとか。いやもう、味噌入り蕎麦のお椀が恋しくなるよ、本当に。
日本――この国だと「食べる」という行為は、ただ体を養うだけのものじゃ全然ない気がする。ただ味わうだけじゃなく、その背後や由緒?大切されている雰囲気、やっぱり独特だな、と。一口ごとになんとなく産地や土、それを生む人の努力……静かな感謝が自分にも芽生えるような。「心して食事を」と昔祖母から何度も言われたっけ。その考えはいまだに離れない。「敬意」なんて言葉、自分でも使っておいて少し照れるけど。でもなあ、日本という場では、自分はいまだ訪問者のままでいるためだけにここに居るような錯覚を起こす瞬間がある。それって、おかしい?異文化への憧れって結局そういう不思議さと裏腹なのかもしれない。
本当に溶け込むってどういうことなんだろう。全部自分の物差しで測れるはずもなく、「触れていい場所」と「永遠に遠巻きでしか見られない部分」を見極め続ける作業、それが"没入"なのかも…。植物学ほど想定外だった発見は他になかったと言える。神奈川県足柄下郡、新仙峡庭園の日は微妙な曇天でさ、着ていたジャケットのファスナー喉元まで上げていたっけ。不意に浮かぶ——マレーシアなら多分布団にもぐりこんで過ごしてたかなとか。いやもう、味噌入り蕎麦のお椀が恋しくなるよ、本当に。

抹茶文化や小さな日常から食体験と心地よさを持ち帰ろう
でも、今日は違う。正直、なんでこんな日なのか分からないけど、植物学の勉強に外へ出たんだ。でもまあ……なんというか、自分は以前にも微妙なミスをしていた気がする。そういえば、この前、苔を思わず踏んでしまったっけ。マレーシアじゃ、苔ってさ、水漏れした壁とか古びた煉瓦にまるで暮れ方の無精髭みたいに広がるカビ扱いされている感じだよね。でも自室にはちょっと岩っぽい置物があって……なんとなく電話しながら、それを「ただの石」としか思わず足を乗せてしまった。そしたら、その砂利や石畳こそ、日本庭園——禅庭園(枯山水)だったってことに、変な間抜けさとともに後になって気付いたんだ。本当にね、自分の浅知恵で昔から続く思想を踏み荒らしてしまった感覚というか、不明を恥じるばかりだった。その後も、人には到底打ち明けられなくて……恥ずかしいし。そして損傷確認までしてみたらさ、どういうわけか苔それ自体も尊い命なのだ、と罪悪めいた重苦しさまで味わった。
きっと本当は理解できていなかったんだろうなあ。禅庭園で苔や石が、それぞれ別々の文化的存在として確固たる意味を持つこととか。言葉みたいだけど言葉じゃない不思議さ。それに、人間だけじゃなく植物も絶えず光・温度・圧力や重力など外部からくる何かしらの信号に反応して動いてるなんて考えてもいなかったんだよね。この日本庭園は静謐と均衡、それから内なる省察、そのすべてを凝縮した空間と言えるような気がする。ただ自然を最小限の要素で表現する潔癖めいた場所。それぞれ——植物、岩、砂利——どれもが「簡素」「質素」「自然性」「非対称」「幽玄」、そして時々混ざる「奇抜さ」と、「静寂」……そんな七つの規範によって、とても細心に配置され調和と静けさと作り上げているようだった。ま、いいか。
きっと本当は理解できていなかったんだろうなあ。禅庭園で苔や石が、それぞれ別々の文化的存在として確固たる意味を持つこととか。言葉みたいだけど言葉じゃない不思議さ。それに、人間だけじゃなく植物も絶えず光・温度・圧力や重力など外部からくる何かしらの信号に反応して動いてるなんて考えてもいなかったんだよね。この日本庭園は静謐と均衡、それから内なる省察、そのすべてを凝縮した空間と言えるような気がする。ただ自然を最小限の要素で表現する潔癖めいた場所。それぞれ——植物、岩、砂利——どれもが「簡素」「質素」「自然性」「非対称」「幽玄」、そして時々混ざる「奇抜さ」と、「静寂」……そんな七つの規範によって、とても細心に配置され調和と静けさと作り上げているようだった。ま、いいか。
日本庭園で苔や石から学ぶ繊細な景観美・自然観察術
ランドスケープデザインで用いられる石は、ほら、自然が生み出したまんまの姿で並べるべきだなんてよく聞くけど——ああ、「そのまま」って意外と難しいものですね。手を加えず、不規則に…絶対一直線にはしちゃダメだって、頭では分かっててもなぜかつい形を整えたくなる気もする。いや、それでもそうすることで本来の風景の質感が失われずに保たれて、どこか内省というか瞑想的な気持ちになる気がするんですよ。不思議だなぁ。あぁ、技術革新とかAIで何でも均一化できる今なのに…やっぱり人は「不揃い」に惹かれるものなのかな?—また脱線してる。でも話を戻すと、日本のリアリズム美学って昔から続いていて、それも素朴さとか控えめなものへの敬意なんですよね。
どうしてこんなことに妙に共鳴してしまうのかわからないけれど、日本庭園って非対称だけどやっぱり計算された配置になっていて、その精密さが逆に自由っぽく映ったりします。「禅庭園」の石や苔を見るたび、自分自身をそこに投影せざるを得ませんでした。不思議と。でね、華やかな繁華街——新宿(兄は好きらしい)のような場所ではなくてさ……静かな竹林、小道沿いの萩、大地いっぱいの様々なミズゴケ。それぞれ違う緑色や湿度の高い空気を感じて歩く時間が、自分でも驚くほど心地よかった。
霧雨が降った日には小さなお茶室へ滑り込んで、季節ごとの和菓子を味わいつつ抹茶もすすりました。この時ばかりは何とも言えぬ深い調和感、本当に「初めて」だと思いましたよ——自分自身とうまく折り合いながら存在できている実感、と言えばいいのでしょうか。それから斜面にふんわり広がるornamental Japanese forest grassという植物を眺めたりもしましたっけ。これ、「ハコネチョウ」だったんです(Hakonechloa macra)。妙に納得した覚えがあります、この名前は神奈川県箱根町由来なんですって。本当に、自分はここ、この場所こそ在るべきところだ……そんな強烈な予感すらしたくらいです。そして同時に、「由来」という発想について日本そのものから教わったようにも感じました。
熱々の抹茶湯呑みを両手で包み込みながら、その静寂と落ち着きだけじゃなくて、瑞々しい緑葉・黄色葉群の微妙な色変化までじっと見つめていたら……体内でほんの少し世界観が転回されるような、不確かな高揚感まで湧き上がってきました。「ま、いいか。」この前頭葉から扁桃体へ伝わる微細な知覚こそ、本場ならではと思わせる禅庭園特有の魔法みたいでした。結局、日本という土地だから経験できたことだった――その余韻だけは今も消えてないです。
どうしてこんなことに妙に共鳴してしまうのかわからないけれど、日本庭園って非対称だけどやっぱり計算された配置になっていて、その精密さが逆に自由っぽく映ったりします。「禅庭園」の石や苔を見るたび、自分自身をそこに投影せざるを得ませんでした。不思議と。でね、華やかな繁華街——新宿(兄は好きらしい)のような場所ではなくてさ……静かな竹林、小道沿いの萩、大地いっぱいの様々なミズゴケ。それぞれ違う緑色や湿度の高い空気を感じて歩く時間が、自分でも驚くほど心地よかった。
霧雨が降った日には小さなお茶室へ滑り込んで、季節ごとの和菓子を味わいつつ抹茶もすすりました。この時ばかりは何とも言えぬ深い調和感、本当に「初めて」だと思いましたよ——自分自身とうまく折り合いながら存在できている実感、と言えばいいのでしょうか。それから斜面にふんわり広がるornamental Japanese forest grassという植物を眺めたりもしましたっけ。これ、「ハコネチョウ」だったんです(Hakonechloa macra)。妙に納得した覚えがあります、この名前は神奈川県箱根町由来なんですって。本当に、自分はここ、この場所こそ在るべきところだ……そんな強烈な予感すらしたくらいです。そして同時に、「由来」という発想について日本そのものから教わったようにも感じました。
熱々の抹茶湯呑みを両手で包み込みながら、その静寂と落ち着きだけじゃなくて、瑞々しい緑葉・黄色葉群の微妙な色変化までじっと見つめていたら……体内でほんの少し世界観が転回されるような、不確かな高揚感まで湧き上がってきました。「ま、いいか。」この前頭葉から扁桃体へ伝わる微細な知覚こそ、本場ならではと思わせる禅庭園特有の魔法みたいでした。結局、日本という土地だから経験できたことだった――その余韻だけは今も消えてないです。

庭園散策を通して植物との対話・人生観へ意識を向けてみよう
日本の植物学、あるいは禅庭園。ふとそんなものに手を伸ばしてしまった結果――食べ物だけが私の好奇心じゃなかった、ということに今さらながら思い至ることもある。まさかここで「場所」と「わたし」を繋ぐ隠喩に出会うとは、ちょっと驚いたというか、そういう予感すらなくて。ただ苔や石…まあ正直その由来とか細かい歴史なんて分からない。でも、不思議とそこの空気、その息づかいみたいなものが伝わってくる瞬間が確かにあって、詩的?いや詩だなんて大げさかな――いやでも、美しかった、としか言えない。で、話は脱線するけど技術者だった自分、自然界の秩序や不完全さにはいつも妙な憧れを抱いてきたんだよね。その一方で静かに座り込むと、「没入」と「観察」…一見反発しあうものが同じ場面で共存しているようにも感じてしまう。それから急に、自分がよそ者とか外野だなんて思わなくなっていた。「畏敬」という感情―それ自体を探し求める人になっていた気がする。禅庭園って教科書以上に多くのことを語っている鏡みたいな存在で、「すべてを征服せず理解へ向ける姿勢」がじわりと胸に残ったりする。
もう何年になるかな……ずっと、「力」や「コントロール」、要するに人生全部の舵取りみたいな強迫観念ばっかり追い続けてきた。でも日本では(これまた妙な話だけど)気づけば50歳近くになって、生き急ぐ癖とか無理につかみ取ろうとしていたモノを徐々に手放す感覚―つまり今この瞬間で良いじゃないか、と受容できた初めての国だった。「本当にこんなの要ったんだっけ?誰のため?」……くだらない反省なんだけどね。橋の上から鯉を見る自分。その流れに漂う鯉たちを眺めながら、凝り固まった執着も少しずつ剥がれて落ちていくようで。そしてふと、「幸福だったと言える時期などあったのか、それとも本当はずっと自分自身との格闘の日々だったんじゃ?」—そんな疑問符まで湧いてきたりする。
これこそ、本当に日本への最初の訪問(兄弟姉妹なら鼻先ひねるくらい興味持たれないだろう類)の中核的な発見だったと思う。一番最初は成田空港へ降り立った瞬間、その広大さや独特な熱気というもの―圧倒される体験だった。それでも和食(washoku)よろしく、この国には形や演出への細やかな配慮・忍耐強さでも評価されるところがある。脱線したつもりでも文化論になるけど、日本独特の連続性意識といえばいいのかな…。日常的な所作や儀礼、その一つ一つにも代々磨き抜かれてきた律儀さや尊重――それら全部が暮らし全体へ透徹していると感じざるを得ない。
もう何年になるかな……ずっと、「力」や「コントロール」、要するに人生全部の舵取りみたいな強迫観念ばっかり追い続けてきた。でも日本では(これまた妙な話だけど)気づけば50歳近くになって、生き急ぐ癖とか無理につかみ取ろうとしていたモノを徐々に手放す感覚―つまり今この瞬間で良いじゃないか、と受容できた初めての国だった。「本当にこんなの要ったんだっけ?誰のため?」……くだらない反省なんだけどね。橋の上から鯉を見る自分。その流れに漂う鯉たちを眺めながら、凝り固まった執着も少しずつ剥がれて落ちていくようで。そしてふと、「幸福だったと言える時期などあったのか、それとも本当はずっと自分自身との格闘の日々だったんじゃ?」—そんな疑問符まで湧いてきたりする。
これこそ、本当に日本への最初の訪問(兄弟姉妹なら鼻先ひねるくらい興味持たれないだろう類)の中核的な発見だったと思う。一番最初は成田空港へ降り立った瞬間、その広大さや独特な熱気というもの―圧倒される体験だった。それでも和食(washoku)よろしく、この国には形や演出への細やかな配慮・忍耐強さでも評価されるところがある。脱線したつもりでも文化論になるけど、日本独特の連続性意識といえばいいのかな…。日常的な所作や儀礼、その一つ一つにも代々磨き抜かれてきた律儀さや尊重――それら全部が暮らし全体へ透徹していると感じざるを得ない。
静寂な日本の空間で自己再発見と年齢による成長に気づく旅へ
どうしてだろう、どこへ行っても祖父母の姿が不意に脳裏をよぎるんだ。子供のころ、なんとなく心惹かれたあの仕草や手つき、ああいう記憶がじんわりと浮上する夜もある。たしかに、自分はここでは「訪れる者」でしかなくて、ずっと腰を落ち着けることなく旅をしている状態、それだけは変わらない気がする。一過性というか…いや、一部が欠けてしまったパズルみたいなものかな。今どきの旅行文化って、「発見」とか「新しさ」を大事にしていて、それ自体は嫌いじゃないけど、この断片的な体験しか積めてないんだよな、とふと思う。そのせいでなのか…言葉にはしづらい変な違和感みたいなものが胸に残る。この土地をどれだけ称賛したとしても、懸命に関わろうとしても、自分は結局よそ者――外から横目で覗いている人間――そんな感覚が消えてくれない時期がずっと続いた。そのギャップというか距離そのものが、実は一番初めに感じた疎外感の理由なのかもしれないと思えてしまうことすらある。
地元の人々はね、不思議と自然体で伝統や生活様式を継承していくでしょう?無理に学ぼうともせず、ごく普通に溶け込んでいる。それなのに、自分と言えば傍観者めいたままで、日本文化なるものを遠巻きに眺めつつ理解しようとしていただけだった。うーん、その距離って単純によく知らない「味」に慣れていないとかいう話とはまた違って、本能的な帰属感とあと付けで磨いた“鑑賞する目”との温度差でもあった。「他のみんな」は疑念すら持たず長く呼吸してきた文化を、自分だけ汗ばみながら必死になぞろうと努力する生徒…笑っちゃうくらいぎこちなくて情けなくなる瞬間も、実際多かった。
そう思いつつ、日本各地の森とか湖とか、本当に静かな景色ばっかり七日間歩き回った日々…これはちょっと奇妙な話なんだけど、そのせいで逆に日本そのものが内側からささやくような存在になった気もする。「あ、これ師匠が弟子探し当てた時みたいだな」、根拠なくそんな例えすら頭をよぎる(笑)。黄色く染まるイロハモミジも季節ごと姿こそ違えど動じず居続ける。そのしぶとさは私にも少し移った気もしなくもない。
庭先で一人ぼーっと座り込みながら、「年齢」……いや厳密には「老い」そのものじゃなくて、自分という全存在(肉体・精神・魂)が重層的につながるあり方について考える。実はヨガ教室なんて通っていた時より、その場その時そのままで居合わせようとしていた時間のほうこそ本物だった、と妙に納得したりして…。滑稽さすらある好奇心が全然足りてなかった、と途中ふと反省した。本当なら、ごちゃごちゃ考えたり知識詰め込む前に、黙ってしゃがみ込んで――文字通り“草木”へ指先伸ばすだけ、それだけ充分だったんじゃないかな、なんて変な腑落ち方までしたんだ。ま、いいか。
地元の人々はね、不思議と自然体で伝統や生活様式を継承していくでしょう?無理に学ぼうともせず、ごく普通に溶け込んでいる。それなのに、自分と言えば傍観者めいたままで、日本文化なるものを遠巻きに眺めつつ理解しようとしていただけだった。うーん、その距離って単純によく知らない「味」に慣れていないとかいう話とはまた違って、本能的な帰属感とあと付けで磨いた“鑑賞する目”との温度差でもあった。「他のみんな」は疑念すら持たず長く呼吸してきた文化を、自分だけ汗ばみながら必死になぞろうと努力する生徒…笑っちゃうくらいぎこちなくて情けなくなる瞬間も、実際多かった。
そう思いつつ、日本各地の森とか湖とか、本当に静かな景色ばっかり七日間歩き回った日々…これはちょっと奇妙な話なんだけど、そのせいで逆に日本そのものが内側からささやくような存在になった気もする。「あ、これ師匠が弟子探し当てた時みたいだな」、根拠なくそんな例えすら頭をよぎる(笑)。黄色く染まるイロハモミジも季節ごと姿こそ違えど動じず居続ける。そのしぶとさは私にも少し移った気もしなくもない。
庭先で一人ぼーっと座り込みながら、「年齢」……いや厳密には「老い」そのものじゃなくて、自分という全存在(肉体・精神・魂)が重層的につながるあり方について考える。実はヨガ教室なんて通っていた時より、その場その時そのままで居合わせようとしていた時間のほうこそ本物だった、と妙に納得したりして…。滑稽さすらある好奇心が全然足りてなかった、と途中ふと反省した。本当なら、ごちゃごちゃ考えたり知識詰め込む前に、黙ってしゃがみ込んで――文字通り“草木”へ指先伸ばすだけ、それだけ充分だったんじゃないかな、なんて変な腑落ち方までしたんだ。ま、いいか。


