失敗談を活かし、後悔しない住宅設備選びと無理なく節約できるコツがわかる
- 見積もりは3社以上取り寄せ、費用差と工事内容の違いを具体的に比較する
10%以上安くなる場合や追加サービス発見で予算圧縮しやすい
- 断熱材や高効率設備への投資額を全体予算の15%以上確保しておく
光熱費が年間20~30%下がり長期で大きな節約効果
- 優先順位リスト作成、絶対譲れない設備ベスト5だけに絞って依頼する
不要な出費を平均20万円以上カットできて満足度も上がる
- (完成後)1週間以内に動線・使い勝手の不具合チェックメモ残す
早期修正交渉で手直し無料対応されやすく損失防止につながる
葉が落ちる住宅街と転職面接の曖昧な記憶
1991年初頭、私はウェスタンオンタリオ大学の教員職の面接を受けていた。なんだかもう遠い昔みたいな気もするけど、その訪問中、不動産業者がロンドン北西部の住宅地に私を連れて行ってくれたんだよね。ああ、そういえば、道すがら何か変な看板があったような気もする…いやいや、それは今関係ないや。
で、そのとき私は、オーチャードパークっていうキャンパスから自転車でも通えそうなくらい静かで緑がいっぱいの分譲地に心底感心してしまったんだ。ほんとうに、緑豊かな場所ってだけで妙に安心できることってあるよね?ま、とりあえず。その後、その職をオファーされて素直に受諾した。でもまあ、その選択が最良だったのかは未だによくわからない。
数か月経って妻のフランシーヌがロンドンへ家探しに行くことになった。しかしねぇ、結局オーチャードパークは我々には到底手が届かない価格帯だった。うーん…現実は厳しい。それでフランシーヌの探索範囲もホワイトヒルズ内の2軒まで絞られた。ところがこの地域、木々もそれほど多くなくて、しかも大学からもちょっと遠かったんだよね。不思議とその距離感というもの、一度住むとなかなか慣れないものさ…。まあいいや。
フランシーヌは物件詳細をファックスで私に送ってきて、それで二人して決断せざるを得なかった。なんとも急ぎ足だった記憶しかない。でも夏の終わりには、一緒にロンドンへ引っ越して新居を手に入れることになったんだ。本当に嵐みたいな数週間だった気分。
さて、その家なんだけど正直言うと外観は全然魅力的じゃなかった:アルミサイディング、大きすぎるくらい目立つガレージ、それなのにメインフロアには通り側につながる窓さえなし。「どういう設計思想なの?」と思わずツッコミたくなる仕様だった。でもこれはもう前もってフランシーヌが撮影した写真のお陰で知っていたし、不満というより苦笑いしか出てこなかった。
ま、本当の意味で不快な驚き――それは玄関から一歩踏み入れて始まったんだ。リビングルームは薄暗くて何とも重苦しい空気漂う感じ。そして壁には漆喰仕上げ…なんとなくだけど、自分でも知らぬ間によそ見ばっかりしてしまう空間。それでも結局ここから新生活が始まったわけだから、人間案外慣れるものさ…。
で、そのとき私は、オーチャードパークっていうキャンパスから自転車でも通えそうなくらい静かで緑がいっぱいの分譲地に心底感心してしまったんだ。ほんとうに、緑豊かな場所ってだけで妙に安心できることってあるよね?ま、とりあえず。その後、その職をオファーされて素直に受諾した。でもまあ、その選択が最良だったのかは未だによくわからない。
数か月経って妻のフランシーヌがロンドンへ家探しに行くことになった。しかしねぇ、結局オーチャードパークは我々には到底手が届かない価格帯だった。うーん…現実は厳しい。それでフランシーヌの探索範囲もホワイトヒルズ内の2軒まで絞られた。ところがこの地域、木々もそれほど多くなくて、しかも大学からもちょっと遠かったんだよね。不思議とその距離感というもの、一度住むとなかなか慣れないものさ…。まあいいや。
フランシーヌは物件詳細をファックスで私に送ってきて、それで二人して決断せざるを得なかった。なんとも急ぎ足だった記憶しかない。でも夏の終わりには、一緒にロンドンへ引っ越して新居を手に入れることになったんだ。本当に嵐みたいな数週間だった気分。
さて、その家なんだけど正直言うと外観は全然魅力的じゃなかった:アルミサイディング、大きすぎるくらい目立つガレージ、それなのにメインフロアには通り側につながる窓さえなし。「どういう設計思想なの?」と思わずツッコミたくなる仕様だった。でもこれはもう前もってフランシーヌが撮影した写真のお陰で知っていたし、不満というより苦笑いしか出てこなかった。
ま、本当の意味で不快な驚き――それは玄関から一歩踏み入れて始まったんだ。リビングルームは薄暗くて何とも重苦しい空気漂う感じ。そして壁には漆喰仕上げ…なんとなくだけど、自分でも知らぬ間によそ見ばっかりしてしまう空間。それでも結局ここから新生活が始まったわけだから、人間案外慣れるものさ…。
壁紙地獄・床下の謎と不思議なカーペットたち
寝室ごとに、どうしてこんなにも違う色のカーペットが?しかもね、それぞれ奇天烈というか…派手な壁紙まで取り合わせてあって、何とも落ち着かない感じだったんだ。ふう、考えてみれば全部の改修や修繕が、まるで「手を抜けるだけ抜いたらこうなる」っていう見本みたいでさ。いや、ほんと笑っちゃうくらい。
例えばさ、エンスイートのパウダールームなんて——ああ、思い出すだけで少し頭が痛い。「カルカッタのブラックホール」って勝手に呼んでたんだけどね。そこは薄っぺらなシート状リノリウムが無造作に敷かれていて(どうでもいい話だけど)、施工した人は巾木を外すことすら面倒だったのか、そのまま貼ったから端っこがめくれてた。わたし、「これは本当に見た目がひどい!」とつぶやいた。でもフランシーヌは「こんなふうだったなんて覚えていないわ!」って不思議そうに言ったんだよね。あれ、不思議だ。
いやまあ、それより強烈だったのは実はダイニングルームだったと思うんだ。カーペット敷きなのに壁には金色模様入りミラータイルを貼り付けてある場違い感!どうにも場末感というか…。えっと、「このタイルはニューオーリンズのキャットハウスで見かけそうだね」なんて冗談めいて言ってみたりしたら、「どうしてそんなこと知っているの?」とフランシーヌに突っ込まれた。それは…まぁ秘密ということで。
ところで家屋内部とか床下も妙な発見ばっかりだったよ。配線はアルミニウム製——つまり火災リスクとして有名なやつ。それから寝室の壁には下塗り処理がされてなくて、壁紙を剥ぐと裏打ち紙もろとも石膏ボード自体まで剥離する始末。本当になんなんだろう、この家。でも一番困ったのはそこじゃなくて…結局、この家には電気式ベースボードヒーターしか設置されてなかったことかな。ナイアガラフォールズから豊富な無料電力が供給されるくせにオンタリオ州では世界でも高水準と言われる電気料金体系になってる。不条理すぎてため息しか出ない日々ですよ、本当にさ…。
例えばさ、エンスイートのパウダールームなんて——ああ、思い出すだけで少し頭が痛い。「カルカッタのブラックホール」って勝手に呼んでたんだけどね。そこは薄っぺらなシート状リノリウムが無造作に敷かれていて(どうでもいい話だけど)、施工した人は巾木を外すことすら面倒だったのか、そのまま貼ったから端っこがめくれてた。わたし、「これは本当に見た目がひどい!」とつぶやいた。でもフランシーヌは「こんなふうだったなんて覚えていないわ!」って不思議そうに言ったんだよね。あれ、不思議だ。
いやまあ、それより強烈だったのは実はダイニングルームだったと思うんだ。カーペット敷きなのに壁には金色模様入りミラータイルを貼り付けてある場違い感!どうにも場末感というか…。えっと、「このタイルはニューオーリンズのキャットハウスで見かけそうだね」なんて冗談めいて言ってみたりしたら、「どうしてそんなこと知っているの?」とフランシーヌに突っ込まれた。それは…まぁ秘密ということで。
ところで家屋内部とか床下も妙な発見ばっかりだったよ。配線はアルミニウム製——つまり火災リスクとして有名なやつ。それから寝室の壁には下塗り処理がされてなくて、壁紙を剥ぐと裏打ち紙もろとも石膏ボード自体まで剥離する始末。本当になんなんだろう、この家。でも一番困ったのはそこじゃなくて…結局、この家には電気式ベースボードヒーターしか設置されてなかったことかな。ナイアガラフォールズから豊富な無料電力が供給されるくせにオンタリオ州では世界でも高水準と言われる電気料金体系になってる。不条理すぎてため息しか出ない日々ですよ、本当にさ…。
Comparison Table:
| 結論 | 詳細 |
|---|---|
| 家の購入プロセス | 予算を考慮し、無理のないオファーを出すことが重要。最初の価格に固執せず、交渉することで良い結果が得られる可能性がある。 |
| 暖房システムのトラブルシューティング | 新しい機器に交換しても古い部品が問題となる場合が多い。特にゾーンバルブや配管は慎重な確認が必要。 |
| 家の増築と温度管理 | 増築部分の暖房は元々の設計と異なるため、注意深く検証しなければならない。専門家による診断を受けることが推奨される。 |
| 感情的なサポート | 家庭内で起こる問題には感情的な影響も大きく、新たなパートナーとの関係構築にもつながる場合がある。 |
| メンテナンスと投資効果 | 長期的には定期的なメンテナンスと適切な修理投資が住環境を快適に保つ鍵となり、その後の生活満足度にも寄与する。 |
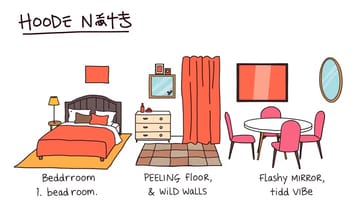
電気代破産寸前から始まるダクトむき出し生活
新しい家に越してから初めての冬、暖房費がどれだけかかるんだろうと正直不安だった。いや、本当に。もしかしたら生活を圧迫するくらいの大きな負担になるんじゃないかな、と夜中に考え込むこともしばしばあった。でも、ふと思いついてベースボードヒーターを取っ払ってみたわけで…なんでそんな思い切りができたのか今でも謎。でもまあ、より効率的な強制送風式システムを導入した結果、電気代はぐっと手頃になったし、ここまでは良かった。ま、いいか。
ただそのお陰というか副作用なのか、巾木には変な隙間ができちゃうし壁や天井にも穴がぽつぽつ空いてて、それにダクトもどういう訳か無造作に露出したままだった。よく見るとさ、この家自体元々けばけばしいタイルとか傷んだカーペットとか、「水瓶座の時代」…妙な懐古主義? なんというかそんな感じの壁紙まであって、本当に修繕箇所は山ほど残されていたわけ。でもそれはともかく、一度話が逸れそうになったので戻すね。
幸運だったのは近くに頼れる人がいたことだ。フランシーヌの父親ニックは住宅建設会社を共同経営していた(この辺りイタリア移民コミュニティならではの話なのかな)。彼自身もイタリアからカナダへ渡った時はたった50ドルしか持っていなくて、とくべつ誇れる技能も無かったみたいなんだけど、「自分は大工として訓練済みです」と現場で言っちゃって、そのまま働きながら技術を身につけていったとか…。いや、それ本当? と今さら疑問湧くけど、多分事実なんだと思う。
その後長年かけて仲間――paesanoと言えば良いかな――と一緒に独立して、自分たちだけの事業を始めることになった。その道程には努力や偶然性、それから自治体政治家への賄賂……これ言ってよかったっけ? まぁ、とにかく色々あって成功して、「ミリオネア」=「住宅所有者」じゃなかった時代なのにも関わらず資産家となるまでになっていた。そのお陰でニック夫妻は毎週末ロンドンまで来る習慣になり、奥さんは孫娘との時間を楽しみにする一方で、本人は休みなく家屋修繕作業に精魂傾けていた。何という勤勉さ。
とは言え、一つ問題があった。それは自分も当然手伝うものとして期待されてしまっていることであり、自分自身はいわゆる器用貧乏タイプでもなく、不器用極まりない部類なのだ。不安定さ丸出し状態になった最初の日――「ハンマー取って」とニックから声掛けされたその瞬間だった。ほんとうに情けない話…。
ただそのお陰というか副作用なのか、巾木には変な隙間ができちゃうし壁や天井にも穴がぽつぽつ空いてて、それにダクトもどういう訳か無造作に露出したままだった。よく見るとさ、この家自体元々けばけばしいタイルとか傷んだカーペットとか、「水瓶座の時代」…妙な懐古主義? なんというかそんな感じの壁紙まであって、本当に修繕箇所は山ほど残されていたわけ。でもそれはともかく、一度話が逸れそうになったので戻すね。
幸運だったのは近くに頼れる人がいたことだ。フランシーヌの父親ニックは住宅建設会社を共同経営していた(この辺りイタリア移民コミュニティならではの話なのかな)。彼自身もイタリアからカナダへ渡った時はたった50ドルしか持っていなくて、とくべつ誇れる技能も無かったみたいなんだけど、「自分は大工として訓練済みです」と現場で言っちゃって、そのまま働きながら技術を身につけていったとか…。いや、それ本当? と今さら疑問湧くけど、多分事実なんだと思う。
その後長年かけて仲間――paesanoと言えば良いかな――と一緒に独立して、自分たちだけの事業を始めることになった。その道程には努力や偶然性、それから自治体政治家への賄賂……これ言ってよかったっけ? まぁ、とにかく色々あって成功して、「ミリオネア」=「住宅所有者」じゃなかった時代なのにも関わらず資産家となるまでになっていた。そのお陰でニック夫妻は毎週末ロンドンまで来る習慣になり、奥さんは孫娘との時間を楽しみにする一方で、本人は休みなく家屋修繕作業に精魂傾けていた。何という勤勉さ。
とは言え、一つ問題があった。それは自分も当然手伝うものとして期待されてしまっていることであり、自分自身はいわゆる器用貧乏タイプでもなく、不器用極まりない部類なのだ。不安定さ丸出し状態になった最初の日――「ハンマー取って」とニックから声掛けされたその瞬間だった。ほんとうに情けない話…。
道具笑い話からイタリア流建築哲学まで一瞬で飛ぶ週末
私が唯一持っていたハンマーを彼に見せた瞬間、彼は吹き出してしまった。「それ、子供用のハンマーじゃないか!」って。なんだよ、ニック、そんな言い方ある?娘婿なのに。うーん、孫がもっと欲しくないのかな、とか一瞬思ったけど…まあ、それは置いておく。その日からというもの、彼は自分で道具箱を持参するようになり、一緒に作業しようと言いながらも実際にはほとんど全部自分でやってしまうんだよね。
リビングとキッチンの間に壁を建てて、そのあとフレンチドアを取り付けたり、新しいダクト工事の部分も木枠で囲い込んだり。しかもカーペットだった床まで剥がしてタイル張りに変えるなんて、大仕事ばっかり。今思えば、「一緒に作業」っていう言葉は少し誇張だった気がするなあ…。いや、本当に私は必要な工具を差し出すくらいしかできなかったわけで。でもね、いつの間にか「スパイク」とか「ツーバイフォー」とかいう謎単語にも慣れてきて、「プラスドライバー」と「ロバートソンドライバー」の違いも何となく理解した頃――まさか自分が大人サイズのハンマーを振るうことになるとは思わなかった。
そうそう、「スパイク」を「ツーバイフォー」にガツンと打ち込む作業まで任されるようになっちゃってさ、自分でもちょっと笑ったよ。ニックは物づくりになると、とことん頑丈さ重視派。それってイタリア人気質なのかな?コロッセオとかパンテオンとか…えっと、これ余談だけど、一世紀建造なのに今日出来たみたいな顔して残ってるじゃない?いや話戻すけど、本当にあいつの作る木枠なんて、自分ぶら下げても壊れないくらいごつかった。その調子でファミリールームにもクローゼット新設。核戦争でも起こったら家族全員ここへ避難できそうだ、と本気で考えたりして。ロンドンがポストアポカリプス化しても、このクローゼットだけ妙に生き残る気配あるんだよね…。ま、それもちょっと妄想入ってるけど。
その後しばらくしてからだろうか――ニックは毎週末娘宅へ来て作業する情熱をゆっくり失いつつあった。不思議なものだよ、人の熱意というやつは…。
リビングとキッチンの間に壁を建てて、そのあとフレンチドアを取り付けたり、新しいダクト工事の部分も木枠で囲い込んだり。しかもカーペットだった床まで剥がしてタイル張りに変えるなんて、大仕事ばっかり。今思えば、「一緒に作業」っていう言葉は少し誇張だった気がするなあ…。いや、本当に私は必要な工具を差し出すくらいしかできなかったわけで。でもね、いつの間にか「スパイク」とか「ツーバイフォー」とかいう謎単語にも慣れてきて、「プラスドライバー」と「ロバートソンドライバー」の違いも何となく理解した頃――まさか自分が大人サイズのハンマーを振るうことになるとは思わなかった。
そうそう、「スパイク」を「ツーバイフォー」にガツンと打ち込む作業まで任されるようになっちゃってさ、自分でもちょっと笑ったよ。ニックは物づくりになると、とことん頑丈さ重視派。それってイタリア人気質なのかな?コロッセオとかパンテオンとか…えっと、これ余談だけど、一世紀建造なのに今日出来たみたいな顔して残ってるじゃない?いや話戻すけど、本当にあいつの作る木枠なんて、自分ぶら下げても壊れないくらいごつかった。その調子でファミリールームにもクローゼット新設。核戦争でも起こったら家族全員ここへ避難できそうだ、と本気で考えたりして。ロンドンがポストアポカリプス化しても、このクローゼットだけ妙に生き残る気配あるんだよね…。ま、それもちょっと妄想入ってるけど。
その後しばらくしてからだろうか――ニックは毎週末娘宅へ来て作業する情熱をゆっくり失いつつあった。不思議なものだよ、人の熱意というやつは…。

妊娠中の妻を横目に手探りリフォーム、トロイ発掘ごっこも混ぜて
今や、結局また一人で作業する羽目になったんだよね。フランシーヌも「手伝う」とは言ってたけど、なんか…いや、実際にはそうでもなくて、再び妊娠したという理由で結局それも不可能になった。まさか自分が原因らしいとか言われても、ちょっと困るし。まあ、それはさておき。
見習い期間を終えていたから、一応住宅改修の基本くらいは身につけたつもり。荒大工仕事とか石膏ボード貼り、それに多少の配線作業と簡単な配管まで、とりあえずできるようになったんだ。でも時々、「こんなので本当に大丈夫かな」と思うこともある。ああ、話が逸れた。
私が単独で取り組んだプロジェクトのひとつに、「ブラックホール・オブ・カルカッタ」の床張り替えがあったんだけど、その派手なピンク色の花柄リノリウムを剥がしてみたら、全く同じリノリウムがもう一層出てきて唖然とした。その下には青いビニルタイルまで重ねられていて、本当に何層構造なのか呆れるしかない感じだった。その瞬間、自分はトロイア遺跡を掘っているシュリーマンじゃないか、と妙な気分にもなったし…。うーん、そんなことより。
その後、自分で壁を作れるくらいには上達したものの、扉を枠に吊す作業だけはどうしても引退したニックに頼むしかなかった。不器用さには自信あるからね…。知る限りでは、自分の造ったその壁はいまだに残っていると思う。でも正直、それでも第三次世界大戦には耐えられないだろうなって想像してしまう。
こういう改修による生活への影響は少なくなかったけど、それでもフランシーヌと私は「これは最初の持ち家だからさ、5年くらい経てばもっと良い住居へ移れるよ」なんて慰め合っていた。しかし1990年代半ばごろになるとオンタリオ州全体が厳しい時期で、その余波は大学部門にも及んだわけで。支援をフランシーヌの両親から受けても、新しい家探しについてちゃんと考え始められたのは9年後だったという…長かった。本当、不思議なものだよね、この人生ってやつは。
見習い期間を終えていたから、一応住宅改修の基本くらいは身につけたつもり。荒大工仕事とか石膏ボード貼り、それに多少の配線作業と簡単な配管まで、とりあえずできるようになったんだ。でも時々、「こんなので本当に大丈夫かな」と思うこともある。ああ、話が逸れた。
私が単独で取り組んだプロジェクトのひとつに、「ブラックホール・オブ・カルカッタ」の床張り替えがあったんだけど、その派手なピンク色の花柄リノリウムを剥がしてみたら、全く同じリノリウムがもう一層出てきて唖然とした。その下には青いビニルタイルまで重ねられていて、本当に何層構造なのか呆れるしかない感じだった。その瞬間、自分はトロイア遺跡を掘っているシュリーマンじゃないか、と妙な気分にもなったし…。うーん、そんなことより。
その後、自分で壁を作れるくらいには上達したものの、扉を枠に吊す作業だけはどうしても引退したニックに頼むしかなかった。不器用さには自信あるからね…。知る限りでは、自分の造ったその壁はいまだに残っていると思う。でも正直、それでも第三次世界大戦には耐えられないだろうなって想像してしまう。
こういう改修による生活への影響は少なくなかったけど、それでもフランシーヌと私は「これは最初の持ち家だからさ、5年くらい経てばもっと良い住居へ移れるよ」なんて慰め合っていた。しかし1990年代半ばごろになるとオンタリオ州全体が厳しい時期で、その余波は大学部門にも及んだわけで。支援をフランシーヌの両親から受けても、新しい家探しについてちゃんと考え始められたのは9年後だったという…長かった。本当、不思議なものだよね、この人生ってやつは。
五年計画は九年へ、家族増えても引っ越せない低迷期の日々
その時までに、私たちは家の表面という表面をすでに全て交換し尽くしていたんだよね。うーん、なんかもう限界っていうか、「これ以上やらないぞ」と心の底で固く誓った瞬間だった。おもちゃのハンマー…あれはもう使わない、絶対に。ま、いいか。次に住む家では何も手を加えたくなかったんだ、本当に。
偶然だったけど、その家と出会った朝のことは今でもなんとなく覚えてる。仕事へ自転車で向かっている途中でさ、Sherwood Forest の通りの端っこに「オープンハウス」って書いてある看板が立っていたんだよ。でも…あれ?今思い返すと、その時少し空腹だった気がする。不思議とそういう記憶だけ鮮明なんだよね。それはともかく、その地域は Orchard Park よりずっと木々が生い茂っていて静かな雰囲気だったから、「ちょっと寄り道してみようかな」と思って道を外れてみた。
そして見つけたその家は、レンガ造りですべて包まれていて、センターホールプランという昔ながらの作り方で建てられていた。一瞬だけ「この感じ好きかも」と心が動いた。その後職場に着いてすぐフランシーヌに電話した。「昼休みに迎えに来てもらえる?」とか言いながら妙にそわそわしてさ。ところが実際には勘違いしてしまったんだ。その家、一般公開じゃなかった。不動産業者専用の内覧会用看板だったなんて…ほんと迂闊。
でもまあ、不運中の幸運というべきなのかな。その物件はまだ特別な準備段階にも入ってなかったけど、持ち主さんが「購入希望者なら見せてもいいですよ」と同意してくれた。それくらい買う人への期待感が強い世界なのかもしれないね。実際、中も外観と同じくらい魅力的と思える部分、多かったし…。うーん、不意打ちみたいな出会い方だったけど、今振り返ると縁めいたものすら感じる日だった気もするよ。
偶然だったけど、その家と出会った朝のことは今でもなんとなく覚えてる。仕事へ自転車で向かっている途中でさ、Sherwood Forest の通りの端っこに「オープンハウス」って書いてある看板が立っていたんだよ。でも…あれ?今思い返すと、その時少し空腹だった気がする。不思議とそういう記憶だけ鮮明なんだよね。それはともかく、その地域は Orchard Park よりずっと木々が生い茂っていて静かな雰囲気だったから、「ちょっと寄り道してみようかな」と思って道を外れてみた。
そして見つけたその家は、レンガ造りですべて包まれていて、センターホールプランという昔ながらの作り方で建てられていた。一瞬だけ「この感じ好きかも」と心が動いた。その後職場に着いてすぐフランシーヌに電話した。「昼休みに迎えに来てもらえる?」とか言いながら妙にそわそわしてさ。ところが実際には勘違いしてしまったんだ。その家、一般公開じゃなかった。不動産業者専用の内覧会用看板だったなんて…ほんと迂闊。
でもまあ、不運中の幸運というべきなのかな。その物件はまだ特別な準備段階にも入ってなかったけど、持ち主さんが「購入希望者なら見せてもいいですよ」と同意してくれた。それくらい買う人への期待感が強い世界なのかもしれないね。実際、中も外観と同じくらい魅力的と思える部分、多かったし…。うーん、不意打ちみたいな出会い方だったけど、今振り返ると縁めいたものすら感じる日だった気もするよ。
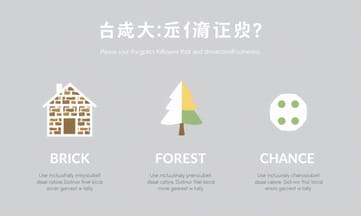
自転車通勤ルートで突然現れた理想の家、でも資金繰りが…
家中のすべてにハードウッドフローリングが張り巡らされていて、クラウンモールディングもあった。大きな窓、それから独立したダイニングルームもね。まあ、どうでもいいけど、玄関の両脇には色ガラスのパネルまで設置されていたんだ。うーん、なんでそんなところに…いや、戻ろう。でも地下室は半分しか完成していなかった。それでも私たちには特に致命的な問題ではなかったんだよね——前に住んでいた家なんて最初から地下室そのものが存在しなかったから。不思議だよなあ。
ただ一つ、本当に困ったことがあってさ。その家の希望価格だけは本当に高額だった。フランシーヌと私には到底手が届かない水準でさ。「ちょっと無理じゃない?」って気分になったよ。結局、控えめなオファーを出してみたんだけど、売主はカウンターオファーを提示してきた。ソファの隙間から小銭を掻き集めるような気持ちで、少しだけ高い金額を提示し直したらさ、またすぐ新しいカウンターオファーが返ってくる始末。まったく…。とはいえ、それでもやっぱり予算的には厳しいままだったんだ。
そこで、不動産業者に「今回は見送ります」と伝えて、一旦気持ちを切り替えた。実際、その後すぐ私は会議のために出張する羽目になったし…どうせなら現実逃避、とか思いつつ数日過ごしていた。そしてニューハンプシャーからフランシーヌへ電話した時、「シャーウッドフォレストの家」の売主が私たち二度目のオファーを受け入れる決断をしたと告げられた。「そんな芸当できる?」と思わず訊いてしまったけど、本当にそうらしかった。その結果として、その住宅を手に入れることになった。
11月初旬、新居へ引っ越し、生活が始まって間もなくあることにふと気づいた。この家には元々建物だった部分に後から増築されたリビングルーム(ファミリールーム)があるんだけど……うん、とても寒い、と感じざるを得なかった。それまで住み慣れてきた家とは違い、この住宅には温水式暖房システムが備わっていた。ただ何故なのかは定かじゃないけれど、その増築された空間だけ温水がラジエータ―まで届いていないようだった。本当に謎だよね。でもまあ、大抵こういうものなのかもしれない、と内心自分をごまかすしかなかった。
ただ一つ、本当に困ったことがあってさ。その家の希望価格だけは本当に高額だった。フランシーヌと私には到底手が届かない水準でさ。「ちょっと無理じゃない?」って気分になったよ。結局、控えめなオファーを出してみたんだけど、売主はカウンターオファーを提示してきた。ソファの隙間から小銭を掻き集めるような気持ちで、少しだけ高い金額を提示し直したらさ、またすぐ新しいカウンターオファーが返ってくる始末。まったく…。とはいえ、それでもやっぱり予算的には厳しいままだったんだ。
そこで、不動産業者に「今回は見送ります」と伝えて、一旦気持ちを切り替えた。実際、その後すぐ私は会議のために出張する羽目になったし…どうせなら現実逃避、とか思いつつ数日過ごしていた。そしてニューハンプシャーからフランシーヌへ電話した時、「シャーウッドフォレストの家」の売主が私たち二度目のオファーを受け入れる決断をしたと告げられた。「そんな芸当できる?」と思わず訊いてしまったけど、本当にそうらしかった。その結果として、その住宅を手に入れることになった。
11月初旬、新居へ引っ越し、生活が始まって間もなくあることにふと気づいた。この家には元々建物だった部分に後から増築されたリビングルーム(ファミリールーム)があるんだけど……うん、とても寒い、と感じざるを得なかった。それまで住み慣れてきた家とは違い、この住宅には温水式暖房システムが備わっていた。ただ何故なのかは定かじゃないけれど、その増築された空間だけ温水がラジエータ―まで届いていないようだった。本当に謎だよね。でもまあ、大抵こういうものなのかもしれない、と内心自分をごまかすしかなかった。
夢叶った瞬間すぐ寒い部屋問題発生、放置されたゾーンバルブ達
配管工を呼ぶことになったんだけど、ああ…そうだ、朝ごはん食べてなかった気がする。まあいいや。本題に戻るね。その配管工が来て「温水暖房があるなんて、ラッキーですよ」と言うわけ。ちょっと拍子抜けだった。どうしてそんなに良いのかって尋ねたら、「放射熱っていうのは強制空気式より“暖かく”感じるんです」みたいな話。でも、えっと…実は私、高校時代に化学少し齧ってさ、熱力学の法則とか一応知ってるつもり。それでも正直、「どんな形態の熱も同じ温度なら“暖かさ”が違う」とは思えなくて。不思議だよね。
それで彼がまた説明を始めた。「ファミリールームと元々のメインフロア半分くらいは別の“ゾーン”になっています」とか言われても、一瞬ぼーっとして聞いてしまった。いや待って、それ何? ああ、ごめん、また脱線しちゃった。つまり、そのゾーンごとに設置されたサーモスタットでバルブ開閉してお湯を流す、と。それ自体は理屈として分からなくもない。
でも結局ね、肝心なところ修理できなかったんだよ、その配管工さん。他社も含め何人試してみても無理だったという話で…もう、この家どうなってるの?とか思いつつ。ただシステム調整してもファミリールームだけ全然寒くて、もう限界きたから諦めてガス暖炉を設置したわけ。これには助けられた。本当に長年その部屋を温めてくれたけど…ただテレビ見る時に送風機の音が微妙にうるさいこともあったかな。ま、それぐらいなら目を瞑れる。
とはいえ、その頃もっと深刻な問題があったんだよね…。主にフランシーヌが癌と診断されたことで――今さら蒸し返すようで嫌なんだけど。その後5年経って彼女が亡くなり、私は再婚して新しい妻(スー)が引っ越してきた。でもスーは「ファミリールームのラジエーター全然温まらない」のを全然当たり前とは思わなかったみたいでさ…。なんか、その反応にも少し救われた気持ちになる、不思議だけど。
それで彼がまた説明を始めた。「ファミリールームと元々のメインフロア半分くらいは別の“ゾーン”になっています」とか言われても、一瞬ぼーっとして聞いてしまった。いや待って、それ何? ああ、ごめん、また脱線しちゃった。つまり、そのゾーンごとに設置されたサーモスタットでバルブ開閉してお湯を流す、と。それ自体は理屈として分からなくもない。
でも結局ね、肝心なところ修理できなかったんだよ、その配管工さん。他社も含め何人試してみても無理だったという話で…もう、この家どうなってるの?とか思いつつ。ただシステム調整してもファミリールームだけ全然寒くて、もう限界きたから諦めてガス暖炉を設置したわけ。これには助けられた。本当に長年その部屋を温めてくれたけど…ただテレビ見る時に送風機の音が微妙にうるさいこともあったかな。ま、それぐらいなら目を瞑れる。
とはいえ、その頃もっと深刻な問題があったんだよね…。主にフランシーヌが癌と診断されたことで――今さら蒸し返すようで嫌なんだけど。その後5年経って彼女が亡くなり、私は再婚して新しい妻(スー)が引っ越してきた。でもスーは「ファミリールームのラジエーター全然温まらない」のを全然当たり前とは思わなかったみたいでさ…。なんか、その反応にも少し救われた気持ちになる、不思議だけど。
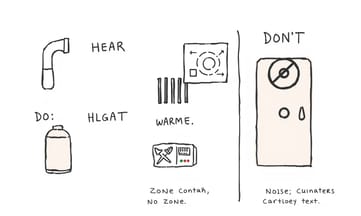
温度論争に終わらぬ配管工巡礼―ガス暖炉騒音と人生激変も挟みつつ
彼女はね、私たちがその全部を修理すべきだと主張していた。うーん、実のところ「全部」って何?って一瞬思ったけど、まあそういうことらしい。それで結局、新しい配管工チームとやり直すことになっちゃったんだよね。ああ、気が重いなあ。
数年の間にさ、この紳士たち(そういえば、一人だけ女性もいた)が色んなパイプとかポンプ、それからバルブにゲージまで、とにかく新品と交換していった。まるで小さな機械の饗宴みたいだった。でも…いや、話が逸れたけど——これだけやってお金も使ったのに、家族部屋のラジエーターはほんの一時だけぬくもるくらい。なんだろうね、この虚しさ。
とは言いつつ、この頃には自分でも暖房システムについて配管業者相手にそこそこ専門的な会話ができるようになってて、それはそれで小さな成長ではあったかも。まあ、別に嬉しくないけど。
問題は増築部分を制御しているゾーンバルブじゃないかと疑ってたんだ。というのも、新しいボイラーが水を加熱して、新しいポンプがその水を他へ送る仕組みだし、新しい配管も設置済みだから、流れを管理するバルブしか疑う余地ないんじゃないかと思えてきて…いや、ごめん、自分でもちょっと混乱した。
それなのに、一連の配管工たちは「テストしました」と胸を張り、そのゾーンバルブは正常ですと言い切るわけ。「見てください、グレームさん、ご自身で試してください。このホイールを回せばいいんです。カチッて音しますよね?それがバルブが開いた合図です」……はいはい。「ほら、ホイールは元通り戻ります。だからゾーンバルブには問題ありません」って説明された。そのあとサラリと「これで三百ドルになります」と請求されてしまった。いやもう、本当に溜息しか出ないよ。
数年の間にさ、この紳士たち(そういえば、一人だけ女性もいた)が色んなパイプとかポンプ、それからバルブにゲージまで、とにかく新品と交換していった。まるで小さな機械の饗宴みたいだった。でも…いや、話が逸れたけど——これだけやってお金も使ったのに、家族部屋のラジエーターはほんの一時だけぬくもるくらい。なんだろうね、この虚しさ。
とは言いつつ、この頃には自分でも暖房システムについて配管業者相手にそこそこ専門的な会話ができるようになってて、それはそれで小さな成長ではあったかも。まあ、別に嬉しくないけど。
問題は増築部分を制御しているゾーンバルブじゃないかと疑ってたんだ。というのも、新しいボイラーが水を加熱して、新しいポンプがその水を他へ送る仕組みだし、新しい配管も設置済みだから、流れを管理するバルブしか疑う余地ないんじゃないかと思えてきて…いや、ごめん、自分でもちょっと混乱した。
それなのに、一連の配管工たちは「テストしました」と胸を張り、そのゾーンバルブは正常ですと言い切るわけ。「見てください、グレームさん、ご自身で試してください。このホイールを回せばいいんです。カチッて音しますよね?それがバルブが開いた合図です」……はいはい。「ほら、ホイールは元通り戻ります。だからゾーンバルブには問題ありません」って説明された。そのあとサラリと「これで三百ドルになります」と請求されてしまった。いやもう、本当に溜息しか出ないよ。
何度目かの修理依頼と空回りする歯車、その後やっと訪れる静かな温もり
現金?それともチェック、それかクレジットカードで…ああ、なんでもいいんだけど。まあ、その話はさておき――というか、シャーロック・ホームズを引き合いに出すのは変かもしれないけど、家の暖房システムってさ、他の部品が全部新しくなっても、たった一つ残された古いパーツが意外とトラブルの元だったりするんだよね。いや、本当にそうなのか自分でも疑問だったけど。結局また配管会社に電話して、「ゾーンバルブを交換しに誰か来てくれません?」って頼んだんだ。うーん、電話口の事務所のお姉さん(声だけじゃ年齢わからない)が言うには、その部品は標準的なやつだから特別注文はいらなくて、多分配管工が車に積んでる、と約束してくれた。でも実際に来た配管工さん、「システムをちょっと見せてもらえます?」とか言い出してさ。えっと、それつまり「診断作業」の名目で余計な料金取ろうとした感じなんだよね……ま、やっぱり予想通りでさ。
ただ最終的にはゾーンバルブが怪しいって認めてくれて――ああ、今思えば最初からそうしてほしかったけど、その時点では在庫持ってなくて後日また来ることになっちゃった。不便極まりない。でも時が経ち、ようやく古いバルブは取り外され、新品ピカピカのものへと置き換えられた。その間、自分でも妙にそわそわしてた気がする。で、片付けながら配管工さん、「ちょっと興味本位で」と呟きながら壊れたゾーンバルブをその場で分解し始める。こういう人いるよね…まぁ助かったけど。そしたら回転する歯車の歯が、本当なら垂直方向についた別のギアと噛み合う仕組みなのに、その見えない方の歯車だけ摩耗していたことが判明した。
だからこっちから見えてる側だけはくるくる動いて、「カチカチ」音も聞こえる。でも実際、中身は全然機能してなかった訳だ。「なるほど」と言いつつ結局また五百ドル支払う羽目になった。痛い出費…。最後は階上へふらっと向かって家族団らん室にあるラジエーターの温まった金属部分に手を当ててみたりした。この手応え――何とも言えず安心するし、不思議と疲れも和らぐ気がする。一件落着……かな?
ただ最終的にはゾーンバルブが怪しいって認めてくれて――ああ、今思えば最初からそうしてほしかったけど、その時点では在庫持ってなくて後日また来ることになっちゃった。不便極まりない。でも時が経ち、ようやく古いバルブは取り外され、新品ピカピカのものへと置き換えられた。その間、自分でも妙にそわそわしてた気がする。で、片付けながら配管工さん、「ちょっと興味本位で」と呟きながら壊れたゾーンバルブをその場で分解し始める。こういう人いるよね…まぁ助かったけど。そしたら回転する歯車の歯が、本当なら垂直方向についた別のギアと噛み合う仕組みなのに、その見えない方の歯車だけ摩耗していたことが判明した。
だからこっちから見えてる側だけはくるくる動いて、「カチカチ」音も聞こえる。でも実際、中身は全然機能してなかった訳だ。「なるほど」と言いつつ結局また五百ドル支払う羽目になった。痛い出費…。最後は階上へふらっと向かって家族団らん室にあるラジエーターの温まった金属部分に手を当ててみたりした。この手応え――何とも言えず安心するし、不思議と疲れも和らぐ気がする。一件落着……かな?


