暮らしやすさと心地よさを高めるヴァーストゥ即実践ヒント
- リビングは東または北東側に大きな窓を設けて毎日30分以上自然光を取り入れる
朝の太陽光で家族の交流が活発になり、気分も明るくなる
- キッチンの調理スペースは南東方向に配置し、調理時には必ず換気扇を稼働させる
火のエネルギーと調和することで健康運や食卓の雰囲気が安定する
- 床・壁・家具など最低2カ所でアースカラー(ベージュや茶色)を使う
五大元素「地」のバランスが整い安心感や集中力アップにつながる
- 玄関ドア周辺は週1回徹底的に掃除し、明るい照明へ交換しておく
"氣" の流れが良くなり開運効果も体感しやすい
日常空間でVastu Shastraの効果を感じる方法
ヴァーストゥ・シャーストラって、近ごろまた妙に注目されてる古代の知恵なんですよね。まあ今さら感もありつつ、「現代の暮らしにも関係あるよ」みたいな話題が出てくると、うっかり耳を傾けたくなる自分がいます。この前はデザイン要素や原則についてアレコレ探った気がするんだけど…えーっと、その延長線上で、初心者向け無料AIツールとかちょっと高難度なAIキャリアへのルート、それから結局基礎的なデザイン原理に戻るみたいな――そんな感じで段々使える道具を揃えてきたんだと思う、多分。
でも今回はヴァーストゥ・シャーストラ、いわゆる“過去の遺産”じゃなくて、「住んでいる部屋をどう見るべきか」のヒントとして取り上げ直そうかな、と急に思いついた次第です。これによって「方向性」とか「エネルギー」、あとは「意図」…そのへんが意外と今まで身につけたこと全部を底上げしてくれる作用してるんじゃないかな。次の記事(タイトルは『How to Apply Vastu - A Practical Guide for Today’s Interiors』になる予定)では、この伝統と時代最先端っぽいツール群との不思議なコンビネーションに焦点当ててみます - 多分ね。
毎日生活する場所って、本当に不思議と人間に響く何か持ってたりしますよね…。ふらっと慣れた部屋に入った瞬間、不意に心境が変わるというか、自覚できないまま小さな波紋が胸中で広がるというか。一方で落ち着きや安堵感になったり、ごく微細だけど消せない違和感となって居座ったり。それこそ久しぶりに子供時代の家へ帰省したときなんか――もう何年振りだろう - 無意識下で記憶の重さみたいなの感じちゃうし、一方で、窓辺から変わらず射す陽の光には「あれ?なんだろこれ」って予想外の解放感も湧いてきたりする。不思議ですよね……ま、いいか。
でも今回はヴァーストゥ・シャーストラ、いわゆる“過去の遺産”じゃなくて、「住んでいる部屋をどう見るべきか」のヒントとして取り上げ直そうかな、と急に思いついた次第です。これによって「方向性」とか「エネルギー」、あとは「意図」…そのへんが意外と今まで身につけたこと全部を底上げしてくれる作用してるんじゃないかな。次の記事(タイトルは『How to Apply Vastu - A Practical Guide for Today’s Interiors』になる予定)では、この伝統と時代最先端っぽいツール群との不思議なコンビネーションに焦点当ててみます - 多分ね。
毎日生活する場所って、本当に不思議と人間に響く何か持ってたりしますよね…。ふらっと慣れた部屋に入った瞬間、不意に心境が変わるというか、自覚できないまま小さな波紋が胸中で広がるというか。一方で落ち着きや安堵感になったり、ごく微細だけど消せない違和感となって居座ったり。それこそ久しぶりに子供時代の家へ帰省したときなんか――もう何年振りだろう - 無意識下で記憶の重さみたいなの感じちゃうし、一方で、窓辺から変わらず射す陽の光には「あれ?なんだろこれ」って予想外の解放感も湧いてきたりする。不思議ですよね……ま、いいか。
室内デザインにVastuエネルギーを活かすコツ
これって…ただの気まぐれな心の揺れと断じられるものじゃないんだよね。空間が知らないうちに私たちの感覚にそっと話しかけてきて、日々の「在り方」を無意識のうちに形づくる - まさにそんな「響き」がある、なんて思わずにはいられない。まあ現代でウェルネスや自分探し系トレンドが流行ってるとか耳にするよりも、はるか昔からインドの古代建築家たちはヴァーストゥ・ヴィディヤ(Vastu Vidya)という知恵を用いて独自に技術を磨いていたみたいで。彼らは、住まいを単なる屋根や壁として扱うどころか、「成功」だとか「調和」だとか──もっと曖昧なのも含めて明晰な暮らしまで能動的に育てようと、その空間自体を工夫していたんだな。それから今、この時代になってAIとかデジタルツールがインテリア業界でもあっさり存在感出してきたりするでしょう(この話は以前の記事でも少し触れてる)。だけど正直言って、“時代超越”系の本質的空間作りには流行ノウハウとは別腹で不可欠なルールみたいなのが隠れている。
## 1. ヴァーストゥ・シャーストラ(Vastu Shastra) - 生き物みたいな科学
ヴァーストゥ・シャーストラ、実際核心になってる問いかけがあるんだ。「どうすれば日常そのものや人生観が環境から自然と支えられたり底上げされたりする?」って。まず、「ヴァーストゥ」はサンスクリット語で“住居”、“シャーストラ”は“理論”または“学”。つまりこれはインド土着で深化したディープな体系ね。ただ運気信仰めいたお守り話でもないし、むろん数学や美観一辺倒とも全然違う。そこには建築学もエコロジーっぽい視点も混じってて、メンタリティや健康への配慮も全部取り込まれているんだ。不思議。
### **ヴァーストゥのおもだった目標**
- 人工的な住居と自然、それから宇宙全体…そういう力との絶妙バランスを生むこと
- 心身健康はもちろん幸福とか富、それから内面成長までジャンジャン促す仕組みづくり
- ストレスや対立、“マイナスの波”みたいなのをできる限り小さく抑えてしまうこと
- とにかく人とその周辺環境とのあいだに前向きな関係性を培うこと
……結局、このヴァーストゥ・シャーストラというのは壮大っぽく見えて案外足元というか、自宅とか都市全域――要するに壁配置ひとつまで宇宙秩序になぞらえて具体化しようぜ!という野心的ガイド、と呼びたくなる。ま、いいか。
## 1. ヴァーストゥ・シャーストラ(Vastu Shastra) - 生き物みたいな科学
ヴァーストゥ・シャーストラ、実際核心になってる問いかけがあるんだ。「どうすれば日常そのものや人生観が環境から自然と支えられたり底上げされたりする?」って。まず、「ヴァーストゥ」はサンスクリット語で“住居”、“シャーストラ”は“理論”または“学”。つまりこれはインド土着で深化したディープな体系ね。ただ運気信仰めいたお守り話でもないし、むろん数学や美観一辺倒とも全然違う。そこには建築学もエコロジーっぽい視点も混じってて、メンタリティや健康への配慮も全部取り込まれているんだ。不思議。
### **ヴァーストゥのおもだった目標**
- 人工的な住居と自然、それから宇宙全体…そういう力との絶妙バランスを生むこと
- 心身健康はもちろん幸福とか富、それから内面成長までジャンジャン促す仕組みづくり
- ストレスや対立、“マイナスの波”みたいなのをできる限り小さく抑えてしまうこと
- とにかく人とその周辺環境とのあいだに前向きな関係性を培うこと
……結局、このヴァーストゥ・シャーストラというのは壮大っぽく見えて案外足元というか、自宅とか都市全域――要するに壁配置ひとつまで宇宙秩序になぞらえて具体化しようぜ!という野心的ガイド、と呼びたくなる。ま、いいか。
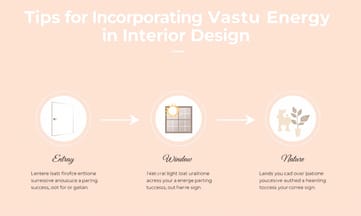
今の暮らしに合うVastu Shastraの基本とは
ヴァーストゥ・シャーストラの起源や、それに関連する古代文献の成り立ちについて考えてみると、実はこのインド伝統建築・デザイン理論は、とてつもなく幅広いヴェーダ典籍とか、叙事詩、あるいは各時代の古典書物などから、設計や施工に関する基本指針を受け継ぎ続けているんですよね。そもそも何千年もの長い歳月をかけて形成された知見で、最初期にはヴェーダ内で登場した祭礼とか宇宙観の言及(正直なところ少し抽象的だったと思う)から始まりました。それが次第に体系化されていき、より具体的で詳細な建築実践論へと姿を変えていったわけです。 - なんだか想像すると壮大すぎて眩暈がします…。ここでは、その歴史的・主題的意義を手掛かりとして、とくに重要だと言われる古代ソースを要点ごとにまとめておきます。
ヴェーダおよびスートラ関係文献
まず「ヴァーストゥ」の理念自体はヴェーダ群に由来していて、その中で土地選びとか方位決定、さらには宇宙秩序との調和(ちょっと神秘的…)などの根本概念が初めて示されています。有名どころとして挙げられるテキスト類には、
- 『リグ・ヴェーダ』『アタルヴァ・ヴェーダ』:たとえば住居守護の神「ヴァストーパティ」への祈願、それから柱立てや墳丘墓づくり、儀礼用構築物なんかにも触れていて、「空間」に対する霊性や呪術的意味づけを与えています(この辺、不思議ですよね)。
- スールバ・スートラ(例:Sulba-Sutras):
ヴェーダおよびスートラ関係文献
まず「ヴァーストゥ」の理念自体はヴェーダ群に由来していて、その中で土地選びとか方位決定、さらには宇宙秩序との調和(ちょっと神秘的…)などの根本概念が初めて示されています。有名どころとして挙げられるテキスト類には、
- 『リグ・ヴェーダ』『アタルヴァ・ヴェーダ』:たとえば住居守護の神「ヴァストーパティ」への祈願、それから柱立てや墳丘墓づくり、儀礼用構築物なんかにも触れていて、「空間」に対する霊性や呪術的意味づけを与えています(この辺、不思議ですよね)。
- スールバ・スートラ(例:Sulba-Sutras):
ヴェーダや古典文献から学ぶVastuの歴史的背景
バウダーヤナやアーパスタンバ(Baudhāyana, Āpastamba)による規則は、紀元前4世紀ごろにまとめられたものだそうで――ああ、なんとなく時代の空気が感じられるな。これら文献には犠牲祭壇を構築するためのかなり細かい幾何学ルールが記されているとされ、それが後になってからヴァーストゥにおける寸法や配置にも深い影響を及ぼしたとか。ちょっと一息…。複雑さと厳密さに目眩しそうだけど、その体系性こそが魅力なのかもしれない。
さて、グリフヤ・スートラ(Gṛhya Sūtras)……例えばシャーンカーヤナ、アーシュヴァラーヤナ、ゴービラ、それからカーディラなどでは、家屋建立のための儀式について驚くほど詳細に書き残されている。まあ本当に…中心柱の位置決めとか扉の配置、それと敷地全体の形状も含まれているんだよね。それぞれ家庭内儀礼としてヴァーストゥをどう扱うか明記してあるっぽい。自宅建築にもこんな徹底した「作法」があったんだと思うと唸っちゃう…。
次に叙事詩・プラーナ系文献について話すね。有名な大規模ヒンドゥー叙事詩とかプラーナ類でもヴァーストゥ原則への言及はちゃんと出てくるという。「物語」の中で都市設計や宮殿・寺院の建築基準について語られてたりして――あぁ、「マハーバーラタ」や「ラーマーヤナ」においてインドラプラスタとかアヨーディヤーみたいな都市が細かく描写され、高い防壁だったり風通し良好な区画割りだったり方角への揃え方なんかまで説明されていた、と伝わる。正直こういう壮大さには圧倒されるしかない。一部のプラーナ文献(Puranas)でも同じような教示例が挙げられてるんだよね。ま、いいか。
さて、グリフヤ・スートラ(Gṛhya Sūtras)……例えばシャーンカーヤナ、アーシュヴァラーヤナ、ゴービラ、それからカーディラなどでは、家屋建立のための儀式について驚くほど詳細に書き残されている。まあ本当に…中心柱の位置決めとか扉の配置、それと敷地全体の形状も含まれているんだよね。それぞれ家庭内儀礼としてヴァーストゥをどう扱うか明記してあるっぽい。自宅建築にもこんな徹底した「作法」があったんだと思うと唸っちゃう…。
次に叙事詩・プラーナ系文献について話すね。有名な大規模ヒンドゥー叙事詩とかプラーナ類でもヴァーストゥ原則への言及はちゃんと出てくるという。「物語」の中で都市設計や宮殿・寺院の建築基準について語られてたりして――あぁ、「マハーバーラタ」や「ラーマーヤナ」においてインドラプラスタとかアヨーディヤーみたいな都市が細かく描写され、高い防壁だったり風通し良好な区画割りだったり方角への揃え方なんかまで説明されていた、と伝わる。正直こういう壮大さには圧倒されるしかない。一部のプラーナ文献(Puranas)でも同じような教示例が挙げられてるんだよね。ま、いいか。
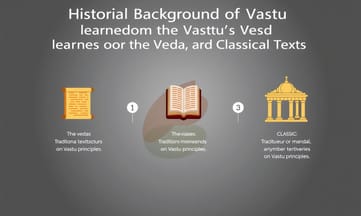
神話・プラーナと現代建築へのつながりを発見する
マツヤ・プラーナやスカンダ・プラーナ、それからアグニ・プラーナ、ガルーダ・プラーナに加えヴィシュヌ・プラーナなんかでもさ、ヴァーストゥの話って、占星術とか儀礼と絡めて紹介されてるんですよね。特に寺院や宮殿をどう設計するか、そのルールが結構細かく記述されていて、何気に読んでいるだけで妙に緊張感が漂うんだよな……こういう古典文献ならではなのかな。
さて、もうちょっと時代を下って5世紀から10世紀頃の、いわゆる古典期には、とりわけヴァーストゥ建築理論に特化したテキストたちも現れてきます。この頃になると都市デザインや住宅のレイアウト、それから寺院造営についてなど、一つにまとまった指針書みたいなものが登場してきて、「なるほど」と唸らせられる内容も少なくないです。…主要なのは以下の通り。
- 『ヴィシュヴァカルマ・プラカーシャ』(Vishvakarma Prakash)という著作(ちなみにヴィシュヴァカルマ名義)。敷地の選び方とか扉の持つ意味合い、更には各種儀礼面をかなり強調している節があって、おそらくは多くの場合基準書として扱われています。
- それと、『アパラジタ・プリッチャ』(Aparajita Prichcha)は—これ実際はヴィシュヴァカルマとアパラジタとの対話形式でまとめられているやつですね—寺院そのものが持つ象徴性とか幾何学的な基本原理をすごく詳しく掘り下げて記しています。
- 『マヤマタ』(Mayamata)(著者はマヤ)は5世紀から7世紀頃の南インド文献なんですけど、建物相互の比例関係とか方角設定、それから有名な「ヴァーストゥ・プルシャ・マンデーラ」の概念まで含め、本当に細部まで説明している気配ありです。
- 次に『マナサーラ・シルパ・シャーストラ』(Manasara Silpa Shastra)。これドラーヴィダ式様式へ特別な視点を置いたものになっており、寸法規定や資材選択—もちろん寺院設計全般まで網羅的と言えるでしょう。ここ、本当によく整理されていますよ。
- あとは『ブリハット・サンヒター』(Brihat Samhita)(作者:ヴァラーハミヒラ/6世紀)。住居配置だったり市街地整備、それに占星術が与える影響までも語っています。ずいぶん包括的ですねぇ…たしかに編集側の意図もうかがえる。
- 最後に取り上げたいのが『サマランガナ・ストゥーラダーラ』(Samarangana Sutradhara)(王ボージャ著作)ですね。11世紀成立とのことですが、公邸はもちろん都市設計、大自然との連携までも織り込んだ章立てで、おそろしく広範囲な議題になっています。「こんな壮大になる?」と内心突っ込みたくなるくらい。
まあ一言で言えば、それぞれ独自色濃厚だけれど、読み比べれば都市や信仰空間形成について複眼的になれるし…案外今にも役立つ知見多し?いやしかし疲れたなぁ。
さて、もうちょっと時代を下って5世紀から10世紀頃の、いわゆる古典期には、とりわけヴァーストゥ建築理論に特化したテキストたちも現れてきます。この頃になると都市デザインや住宅のレイアウト、それから寺院造営についてなど、一つにまとまった指針書みたいなものが登場してきて、「なるほど」と唸らせられる内容も少なくないです。…主要なのは以下の通り。
- 『ヴィシュヴァカルマ・プラカーシャ』(Vishvakarma Prakash)という著作(ちなみにヴィシュヴァカルマ名義)。敷地の選び方とか扉の持つ意味合い、更には各種儀礼面をかなり強調している節があって、おそらくは多くの場合基準書として扱われています。
- それと、『アパラジタ・プリッチャ』(Aparajita Prichcha)は—これ実際はヴィシュヴァカルマとアパラジタとの対話形式でまとめられているやつですね—寺院そのものが持つ象徴性とか幾何学的な基本原理をすごく詳しく掘り下げて記しています。
- 『マヤマタ』(Mayamata)(著者はマヤ)は5世紀から7世紀頃の南インド文献なんですけど、建物相互の比例関係とか方角設定、それから有名な「ヴァーストゥ・プルシャ・マンデーラ」の概念まで含め、本当に細部まで説明している気配ありです。
- 次に『マナサーラ・シルパ・シャーストラ』(Manasara Silpa Shastra)。これドラーヴィダ式様式へ特別な視点を置いたものになっており、寸法規定や資材選択—もちろん寺院設計全般まで網羅的と言えるでしょう。ここ、本当によく整理されていますよ。
- あとは『ブリハット・サンヒター』(Brihat Samhita)(作者:ヴァラーハミヒラ/6世紀)。住居配置だったり市街地整備、それに占星術が与える影響までも語っています。ずいぶん包括的ですねぇ…たしかに編集側の意図もうかがえる。
- 最後に取り上げたいのが『サマランガナ・ストゥーラダーラ』(Samarangana Sutradhara)(王ボージャ著作)ですね。11世紀成立とのことですが、公邸はもちろん都市設計、大自然との連携までも織り込んだ章立てで、おそろしく広範囲な議題になっています。「こんな壮大になる?」と内心突っ込みたくなるくらい。
まあ一言で言えば、それぞれ独自色濃厚だけれど、読み比べれば都市や信仰空間形成について複眼的になれるし…案外今にも役立つ知見多し?いやしかし疲れたなぁ。
代表的なヴァーストゥ経典で家づくりの知恵を広げよう
他にも忘れがちな文献と言えば、ラージャヴァッラバやシルパ・プラカーシャ(だいたい9~10世紀頃、特にオリッサ地方の寺院スタイルにぐっと焦点を絞ったテキスト)、さらにはイシャナシヴァグルデーヴァ・パッドハティ(こっちも9世紀)がよく名前に挙がるんですよね。これらはヴィシュワカルマだとかマヤ、それにブラフマーなどの聖賢たちに由来するとされることが多くて、正直その辺り神話めいて曖昧な感じも否めないけど、まあ本家本元のヴァーストゥ規範として扱われています。五大元素や世界と結びついた力との一致―そういうテーマがひたすら前面に押し出されているし、今でも研究や実践で何かと参照され続けている一方、その解釈は土地ごとだったり宗派によってかなり異なるんですよね。不思議なくらい。
## 3. 哲学的基盤:大地、宇宙、人間体験
そもそもヴァーストゥって、「台所どこ置く?」みたいな単純な話というより(いや、それも大事だけど)、生活全般を普遍的秩序とか調和…その辺とうまく合わせようっていう、結構広い観点のアプローチなんですよ。個人的にもそこには妙なリアリティを感じたりします。
### パンチャ・ブータス(五大元素):
- _大地(プリトヴィ)_:揺るぎない土台となったり支えになって、自分を養ってくれるもの。
- _水(ジャラ)_:流れゆく柔軟さ、ときには浄化して整える側面を持つし、一言で片付かない適応力ですね。
- _火(アグニ)_:エネルギッシュで変化を促す原動力、しかもちょっと楽観的な雰囲気まで帯びてる。
- _空気(ヴァーユ)_:常に動き続け、生への活力となったり、互いの伝達手段にも関わっています。
- _空間(アーカーシャ)_:ただ広がるだけじゃなく、モノや人々のつながり、それから精神性―見過ごせませんよね。
こんなふうに、それぞれの要素が一番いい形で生かされるよう配置する…それこそがヴァーストゥ設計では重要ポイントとして取り沙汰されます。ま、いいか。でもこの5要素意識、本当に現代にも根強く残っています。
## 3. 哲学的基盤:大地、宇宙、人間体験
そもそもヴァーストゥって、「台所どこ置く?」みたいな単純な話というより(いや、それも大事だけど)、生活全般を普遍的秩序とか調和…その辺とうまく合わせようっていう、結構広い観点のアプローチなんですよ。個人的にもそこには妙なリアリティを感じたりします。
### パンチャ・ブータス(五大元素):
- _大地(プリトヴィ)_:揺るぎない土台となったり支えになって、自分を養ってくれるもの。
- _水(ジャラ)_:流れゆく柔軟さ、ときには浄化して整える側面を持つし、一言で片付かない適応力ですね。
- _火(アグニ)_:エネルギッシュで変化を促す原動力、しかもちょっと楽観的な雰囲気まで帯びてる。
- _空気(ヴァーユ)_:常に動き続け、生への活力となったり、互いの伝達手段にも関わっています。
- _空間(アーカーシャ)_:ただ広がるだけじゃなく、モノや人々のつながり、それから精神性―見過ごせませんよね。
こんなふうに、それぞれの要素が一番いい形で生かされるよう配置する…それこそがヴァーストゥ設計では重要ポイントとして取り沙汰されます。ま、いいか。でもこの5要素意識、本当に現代にも根強く残っています。

五大元素との調和で居心地が良くなる理由を探す
方向の科学、つまり「ディシャ」っていう考え方ではさ、太陽が通る道筋とか支配的な風向き、それから地磁気みたいな自然条件が、家の中でどの方位に何を置くべきか決めてるとされているんだよ。北東っていうのは夜明けとともに太陽が顔を出す場所らしくて、新しい力が湧いてくるピュアな方角――要するに瞑想したり水場を設けたりするには理想的なんだって。ふーん、意外と理屈っぽい?ま、ともかくだ。
逆に南東側はというと、朝の日差しがガンガン当たって、一番熱エネルギーを受けやすいところなので台所(キッチン)が一番しっくり来るらしい。ああもう、この分類、思わず唸っちゃうね…。
で、「ヴァストゥ・プルシャ・マンダラ」――宇宙グリッドと言われるものでは、不動産や敷地全体を壮大な宇宙秩序になぞらえて区画ごとの格子(グリッド)が引かれるんだけど、その図柄には伝説上の精霊「ヴァストゥ・プルシャ」が登場していて…この精霊は頭が北東で足は南西の方へ伸びているという妙な形になっている。妙ですよね?
ちなみにグリッド内それぞれのセクションには固有の意味とか機能が与えられていて、それぞれ神々だったり自然現象だったり、結構抽象的なのよね。しかし、本質的なポイントとして「空間」というもの自体が人間の感情や活力、人付き合いまで影響してくる――そんな思想が基盤になっている。一見してオカルト混じりだけど、実際は光や空気、水、それから建物自体の割合なんかにも配慮する科学的視点もセットで採用されていて……結局、人間に目では捉えづらい流れとか微細な作用みたいな精神性まで重きを置く独特の美学が根付いているようだ。うーん、不思議というほかないよね。ま、いいか。
逆に南東側はというと、朝の日差しがガンガン当たって、一番熱エネルギーを受けやすいところなので台所(キッチン)が一番しっくり来るらしい。ああもう、この分類、思わず唸っちゃうね…。
で、「ヴァストゥ・プルシャ・マンダラ」――宇宙グリッドと言われるものでは、不動産や敷地全体を壮大な宇宙秩序になぞらえて区画ごとの格子(グリッド)が引かれるんだけど、その図柄には伝説上の精霊「ヴァストゥ・プルシャ」が登場していて…この精霊は頭が北東で足は南西の方へ伸びているという妙な形になっている。妙ですよね?
ちなみにグリッド内それぞれのセクションには固有の意味とか機能が与えられていて、それぞれ神々だったり自然現象だったり、結構抽象的なのよね。しかし、本質的なポイントとして「空間」というもの自体が人間の感情や活力、人付き合いまで影響してくる――そんな思想が基盤になっている。一見してオカルト混じりだけど、実際は光や空気、水、それから建物自体の割合なんかにも配慮する科学的視点もセットで採用されていて……結局、人間に目では捉えづらい流れとか微細な作用みたいな精神性まで重きを置く独特の美学が根付いているようだ。うーん、不思議というほかないよね。ま、いいか。
方位と自然エネルギーが部屋割りにどう影響するか理解する
ヴァーストゥの基本となる考え方は、建物がどう調和し、その空間を流れるエネルギー(プラーナとか?)を大事にしていこう――まあ、そういう感じだ。たとえば土地選びだけど、昔から四角や長方形みたいな素直な形が好ましくて、とりわけ北東に少し傾いた区画だと「運気が巡る」なんて話もあるらしい。でもね、そんな理想的なの日本で見つかるのかな…ちょっと疑問。
あとさ、玄関とか家の方角って意外に大切らしい。特に出入り口は縁起のいい方向につくるとうまくいく、と信じている人、多いよね。理由は、「気」の入り口だからなのか…何となく納得できなくもない。南東側ならキッチンや配線・電気設備、西南には主寝室や重たい家具・保管スペース。北西部分には客間とか穀類収納っていう割り振りになったりする。その一方で中心部―ブラフマスタンと言うんだけどさ―ここはごちゃごちゃ物を置かずスッキリ開放的な状態がいいとされる。「家そのものの要」に当たるというわけだね。
次に換気と光取り込みについてだけど…これ地味にめんどくさい話かもしれない。北側や東側はなるべく風通しや明るさを確保、それに対して南・西は必要なら遮って熱量調節するのがコツ、って教えられる。「まあ、本当にそんなうまくいく?」ってぼやきたくなる時もある…。Ayadi Shadvargaという比率算定法まであって、文献によれば長さ幅、高さ扉窓寸法など細かな決まりがちゃんとある。それら設計寸法を家主自身のホロスコープとも絡めたりして、オーダーメイドっぽくアレンジされてる場合も珍しくない(昔から不思議だと思ってた)。
さて、それでもヴァーストゥ人気が根強いわけ?近年になりホリスティックウェルネス志向やサステナブル暮らしなんて言葉まで登場し、「科学的根拠」という理由づけでも現代設計学との共通点が強調されつつある。不思議じゃない?実際換気・採光・心身快適性その他にも配慮したガイドラインとして認識され始めている、と個人的にも感じる時多いかな。一見古臭そうで意外と最先端…変な感じ!
あとさ、玄関とか家の方角って意外に大切らしい。特に出入り口は縁起のいい方向につくるとうまくいく、と信じている人、多いよね。理由は、「気」の入り口だからなのか…何となく納得できなくもない。南東側ならキッチンや配線・電気設備、西南には主寝室や重たい家具・保管スペース。北西部分には客間とか穀類収納っていう割り振りになったりする。その一方で中心部―ブラフマスタンと言うんだけどさ―ここはごちゃごちゃ物を置かずスッキリ開放的な状態がいいとされる。「家そのものの要」に当たるというわけだね。
次に換気と光取り込みについてだけど…これ地味にめんどくさい話かもしれない。北側や東側はなるべく風通しや明るさを確保、それに対して南・西は必要なら遮って熱量調節するのがコツ、って教えられる。「まあ、本当にそんなうまくいく?」ってぼやきたくなる時もある…。Ayadi Shadvargaという比率算定法まであって、文献によれば長さ幅、高さ扉窓寸法など細かな決まりがちゃんとある。それら設計寸法を家主自身のホロスコープとも絡めたりして、オーダーメイドっぽくアレンジされてる場合も珍しくない(昔から不思議だと思ってた)。
さて、それでもヴァーストゥ人気が根強いわけ?近年になりホリスティックウェルネス志向やサステナブル暮らしなんて言葉まで登場し、「科学的根拠」という理由づけでも現代設計学との共通点が強調されつつある。不思議じゃない?実際換気・採光・心身快適性その他にも配慮したガイドラインとして認識され始めている、と個人的にも感じる時多いかな。一見古臭そうで意外と最先端…変な感じ!
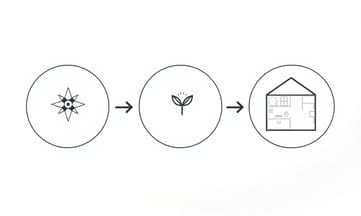
土地選び・採光など具体的なVastu設計ポイントに注目しよう
ヴァーストゥ(Vastu)の魅力は、何といってもその融通無碍さにある。アパートやオフィス、それから古めかしい家屋にもね、不思議なほどしっくり溶け込むんだよなあ。例えばだが…北東の片付けとかベッドの配置替え、それに換気をちょっと見直すだけで、一見小さな手間なのに、思いもよらぬほど空間の居心地が変わることだって本当にあるのだ。まあ、侮れないぞ。しかも、この発想自体が、今や世界中のインテリアデザイナーたちにも意識的に取り入れられていて、秩序・静けさ・ほんわかした豊かさみたいなものを呼び寄せるエッセンスになってたりするらしい。
ヴァーストゥ・シャーストラ(Vastu Shastra)は決してガチガチのお約束事というより、自然との共鳴感とか精神的バランスみたいな雰囲気を大事にする“スタンス”なんじゃないかって気がしている。「こうしなくちゃいけない」じゃなく、「こんなのもありかな?」という余裕、とでもいうべきか…いやまあ、解釈はいろいろあれど。そのうち、伝統的知識とAI技術をうまく掛け合わせて、設計図から仕上げ作業までどうステップ踏んで実際にヴァーストゥを暮らしへ落とし込めるか、その辺も少しずつ記事として掘り下げていくつもりだ。この「目に見えるもの」と「見えざるもの」、「長年受け継がれてきた智恵」と「現代人の日々の要請」を結ぶ架橋こそ、本当に優れたデザインの核なんじゃないかな…。ま、いいか。
ヴァーストゥ・シャーストラ(Vastu Shastra)は決してガチガチのお約束事というより、自然との共鳴感とか精神的バランスみたいな雰囲気を大事にする“スタンス”なんじゃないかって気がしている。「こうしなくちゃいけない」じゃなく、「こんなのもありかな?」という余裕、とでもいうべきか…いやまあ、解釈はいろいろあれど。そのうち、伝統的知識とAI技術をうまく掛け合わせて、設計図から仕上げ作業までどうステップ踏んで実際にヴァーストゥを暮らしへ落とし込めるか、その辺も少しずつ記事として掘り下げていくつもりだ。この「目に見えるもの」と「見えざるもの」、「長年受け継がれてきた智恵」と「現代人の日々の要請」を結ぶ架橋こそ、本当に優れたデザインの核なんじゃないかな…。ま、いいか。
今も活きるVastu Shastraでウェルネス住宅づくりを楽しもう
ヴァーストゥ(Vastu)の精神って、本当に奥が深いんですよね。うーん、これこそが次世代インテリアデザインの原点なのかもしれません。いや、なんとなくですが…この空気感、やっぱり心地よいです。自分自身で実際に試したエピソードとか、不思議に感じたこと、ときどきありませんか?良かったら、下のコメント欄でみなさんの経験を聞かせてほしいなあ、と本音で思っています。何気ない日常にちょっとした発見が転がっているものですし、それを誰かと分かち合うだけで微笑ましくなったりしますしね……うっかり笑っちゃったりして(笑)。そうだ、「Buy Me A Coffee! ☕」からご支援も歓迎ですので、ふと思い立ったらどうぞ。ま、いいか。


