計画外の街歩きでハイデルベルクを深く味わうための即実践ヒント
- 地図やスマホを一旦しまい、30分以上は目的地なしで旧市街を歩いてみる。
偶然の路地や意外な風景と出会える確率が上がり、新しい発見につながるから。
- 旅行中、一度は観光ガイドに頼らず5カ所以上気になる店や建物に自分の直感で立ち寄る。
有名スポット以外にも自分だけのお気に入りが見つかり、旅の思い出が増える。
- (雨でも晴れでも)1時間以内に現地ならではの屋台グルメかドリンクを試してみる。
季節限定や土地特有の味、食文化との偶然の出会いで旅情が一層深まるため。
- (写真より体験重視)30分間はスマホ撮影せず五感だけで城跡や石段など歴史的エリアを巡ろう。
`スクリーン越しじゃない`空気感・音・匂いまで丸ごと感じられるから記憶にも残りやすい。
偶然の道、計画外のハイデルベルクで感じたもの
期待値が低いと、旅って逆に素晴らしく感じることもあるんだよなあ。いや、これは本当に。たぶん誰かもそんなこと言ってた気がするけど、ああ、【ハイデルベルク城。著者撮影。】とかつけると急に現実味が増すね。
ふと立ち寄った場所には、妙に惹かれる不思議な力が隠れてたりするんだよな…なんて考えてたら、お腹すいたな、とか思ってしまう。でもまあ、それは「人のいない裏道を歩け」みたいな話じゃなくてさ。そういえば、ハイデルベルクってドイツで51番目に大きい都市だったっけ?だから全然僻地とかじゃないわけで。
この町には欧羅巴でも有数の歴史や伝統を持つ大学があるし、「ドイツのオックスフォード」だとか「ドイツ版ハーバード」なんて呼ばれたりもするらしいね。ちょっと過剰評価かなと思いつつも、本当にそう言われてるから仕方ないか。
それで、この大学からはマックス・ヴェーバーやハンナ・アーレント、それからロベルト・シューマンやW.サマセット・モーム、それにドミトリ・メンデレーエフまで名だたる人物が出ているわけだけど――えっと、自分でも今誰を書いたか一瞬忘れそうになった。でも結局、この場所自体を最初から目指して来たわけじゃなかったんだよね。不思議だけど、人間って予定外のところで一番心動かされること、多い気がする。ま、いいか。
ふと立ち寄った場所には、妙に惹かれる不思議な力が隠れてたりするんだよな…なんて考えてたら、お腹すいたな、とか思ってしまう。でもまあ、それは「人のいない裏道を歩け」みたいな話じゃなくてさ。そういえば、ハイデルベルクってドイツで51番目に大きい都市だったっけ?だから全然僻地とかじゃないわけで。
この町には欧羅巴でも有数の歴史や伝統を持つ大学があるし、「ドイツのオックスフォード」だとか「ドイツ版ハーバード」なんて呼ばれたりもするらしいね。ちょっと過剰評価かなと思いつつも、本当にそう言われてるから仕方ないか。
それで、この大学からはマックス・ヴェーバーやハンナ・アーレント、それからロベルト・シューマンやW.サマセット・モーム、それにドミトリ・メンデレーエフまで名だたる人物が出ているわけだけど――えっと、自分でも今誰を書いたか一瞬忘れそうになった。でも結局、この場所自体を最初から目指して来たわけじゃなかったんだよね。不思議だけど、人間って予定外のところで一番心動かされること、多い気がする。ま、いいか。
フライブルクへの長いドライブと99ユーロの選択肢
実を言うとね、私たちってドイツに行く予定なんて、全然なかったんだよ。ああ、まあ、トゥールーズで借りたキャンピングカーを返すためにフライブルクには寄らなきゃいけなかった、それはそう。でも、本当の目的はと言えばさ、アルザス地方だったわけよ。ストラスブールとかコルマールとか…その辺りに点在する中世の町々で開催されるクリスマスマーケットを巡るつもりだったんだ、えっと、それが最初の計画。
ただね、不思議と時間だけは余ってたんだよね。ま、そのせいかもしれないけど、この旅では妙に自由度が高い選択肢も出てきたりしてさ。一週間99ユーロでレンタルできて、しかも指定された日に会社が決めた場所まで返却すればいいタイプのキャンピングカーがあったんだよ。えーと…普段ならもっとカチッとしたプラン立てる性分なんだけど、最近の旅行では即興的というかアドリブ多めになってきちゃった。不安になることもあるけど、やっぱり移動式の家のおかげで柔軟にいろんなこと対応できるっていう利点も大きいしね……今さら何話してたっけ?そうそう、その自由さがなんか新鮮だったんだよ。
ただね、不思議と時間だけは余ってたんだよね。ま、そのせいかもしれないけど、この旅では妙に自由度が高い選択肢も出てきたりしてさ。一週間99ユーロでレンタルできて、しかも指定された日に会社が決めた場所まで返却すればいいタイプのキャンピングカーがあったんだよ。えーと…普段ならもっとカチッとしたプラン立てる性分なんだけど、最近の旅行では即興的というかアドリブ多めになってきちゃった。不安になることもあるけど、やっぱり移動式の家のおかげで柔軟にいろんなこと対応できるっていう利点も大きいしね……今さら何話してたっけ?そうそう、その自由さがなんか新鮮だったんだよ。
Comparison Table:
| 観光地 | 特徴 | 受容度 | 歴史的背景 | 現代の影響 |
|---|---|---|---|---|
| ハイデルベルク城 | 部分的に廃墟、風情がある | 新しいアイデアを受け入れやすい町 | 17世紀にフランス軍による破壊があった | 観光客の流入、特にアメリカ人が多い |
| クリスマスマーケット | 伝統的なグリューワイン以外にもホットテキーラなどの新しい飲み物も提供されている | 若者(大学生)の割合が高いことから新しさを受け入れる傾向が強いかもしれない | ||
| プルドポークサンドイッチとコオロギバーガーの屋台 | ベジタリアン向けメニューや昆虫食を取り入れている屋台も存在する | |||
| 観光体験についての考察 | 旅行は計画なしで寄り道しながら楽しむことに価値があると感じるようになった。写真では得られない本当の体験を重視するようになっている。 |
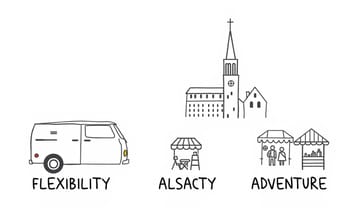
地図を広げる指先、ストラスブールから1時間半だけど何も知らない町へ
地図を広げてみたんだよね。正直、ハイデルベルクなんて全然知らなかった。でも、ストラスブールの拠点から車で1時間半くらいで行けるって気づいた時、ああ、案外近いなとぼんやり思った。ライン川を一跨ぎして、そのあとアウトバーンに乗れば、まあ…バケットリストに書きもしてない新しい場所へたどり着くことくらいはできそうだという感覚があった。それ以上のことは期待しなくてもいいかも。いや、ちょっと待って?そういう肩肘張らない姿勢こそが、実は世界を生き抜くコツなのかもしれない、とふと考えてしまう。
さて、ハイデルベルクの学生たちはどうだったんだろう。彼らには妙に考える時間が多かったらしい、と伝え聞く。それもこれも1780年代から1914年まで続いていたシュトゥーデンテンカルツァー――つまり学生監獄――に入れられていた時期の話なんだけどさ。夜中の騒ぎや酔っぱらい、それから器物損壊みたいな些細(いや些細と言っていいのかわからないけど)な罪で学部生が収容されていたという。不意に別の国の監獄とか想像しちゃうけど…いや違った、これはアブグレイブ刑務所とはまるで別物だったらしいのでご安心を。
さて、ハイデルベルクの学生たちはどうだったんだろう。彼らには妙に考える時間が多かったらしい、と伝え聞く。それもこれも1780年代から1914年まで続いていたシュトゥーデンテンカルツァー――つまり学生監獄――に入れられていた時期の話なんだけどさ。夜中の騒ぎや酔っぱらい、それから器物損壊みたいな些細(いや些細と言っていいのかわからないけど)な罪で学部生が収容されていたという。不意に別の国の監獄とか想像しちゃうけど…いや違った、これはアブグレイブ刑務所とはまるで別物だったらしいのでご安心を。
学生監獄?酔っぱらいや悪戯者が残した落書きだらけの壁たち
あの頃さ、学生たちって――まあ、ほとんどが裕福な家の息子だったんだけど――食べ物とか飲み物、もう欲しいと思ったものは大体注文できたんだよね。なんか不思議な話だけど、実際にはしごやペンキ用の刷毛まで手に入れてたりして……ま、それもまた妙な感じ。そういうわけで、本当に彼らは欲望のままに色々頼んじゃったらしい。あっ、いや、今考えると贅沢すぎる気もするけど。でもまあ、それが普通だったみたい。
それでさ、彼らは一般的に短い刑期を持て余していたから、その暇な時間をうまく使って、自分たちが閉じ込められている監獄の至るところを絵でいっぱいにしたんだよね。ふっと思い出したけど、この「絵」って言葉じゃ伝わりきれない面白さがある気がする…あ、ごめん話逸れた。この空間には落書きやシルエットなんかも見つけることができて、本当に自由奔放というかカオスというか…。あーもう、とにかく筆者自身もその現場(ハイデルベルクの学生監獄内の一室)で撮影した時には、「えっこれ全部学生?」って心底驚いた覚えがある。
それでさ、彼らは一般的に短い刑期を持て余していたから、その暇な時間をうまく使って、自分たちが閉じ込められている監獄の至るところを絵でいっぱいにしたんだよね。ふっと思い出したけど、この「絵」って言葉じゃ伝わりきれない面白さがある気がする…あ、ごめん話逸れた。この空間には落書きやシルエットなんかも見つけることができて、本当に自由奔放というかカオスというか…。あーもう、とにかく筆者自身もその現場(ハイデルベルクの学生監獄内の一室)で撮影した時には、「えっこれ全部学生?」って心底驚いた覚えがある。
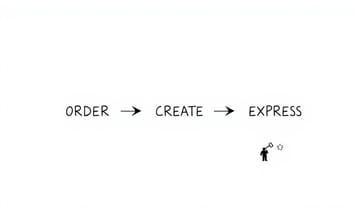
1914年に閉じた牢屋、若者たちの痕跡と奇妙なカップルとの遭遇
名前や日付、それに犯罪と刑期のリスト、さらにあの有名なダンテの「ここに入る者は一切の希望を捨てよ」なんて言葉まで壁に残っている――うーん、この比較的快適な紳士用拘置所にはちょっと場違いかなと思わずにはいられない。でも、全部冗談として受け止めてるみたいで。ま、いいか。今となっては、百年前の学生たちが遺した美しい筆跡や妙に芸術的な技術を眺めることもできるし。えっと、自分は歴史そんな詳しくないけど、「1914年」っていう刑務所閉鎖の日付を見るだけで、何か心がずしんと重くなる気がする。その年になぜ囚人たちが解放されて、生き生きとした学生たちが大陸全体へ向かったのか……いや、それって実際、とても暴力的な形で文化交流(?)が行われたからだと思い出させられる。話逸れちゃったな。それから階段を上り切ったところで、不意に若いカップルが互いの顔を夢中でむさぼり合っていて——しかもその音までかなり大胆だった。ああいう趣味も世にはあるものなのだろう。
ハイデルベルクではクリスマスマーケットも見逃せなくてね。
そして、この辺り一帯というかヨーロッパ各地でクリスマスマーケット巡りをしていた私たちは、ここも外すわけにはいかなかったんだよね。屋台は色鮮やかだし、その雰囲気にもついつい引き込まれてしまった。あ、そうそう、以前にも感じたことなんだけど…ドイツ人ってこういう催しごと、本当に得意なのでは? ふと頭によぎった。でも国境越えればフランス側でも有名なクリスマスマーケットはいくらでもあるし、その _vin chaud_(ホットワイン)やプレッツェルとか _choucroute_(ザワークラウト)なんかとも比べちゃう自分がいる。それぞれ独特だけど…ええと、思わぬ場面だった気もする。また脱線してしまった。でもまあ楽しかったから良し!
ハイデルベルクではクリスマスマーケットも見逃せなくてね。
そして、この辺り一帯というかヨーロッパ各地でクリスマスマーケット巡りをしていた私たちは、ここも外すわけにはいかなかったんだよね。屋台は色鮮やかだし、その雰囲気にもついつい引き込まれてしまった。あ、そうそう、以前にも感じたことなんだけど…ドイツ人ってこういう催しごと、本当に得意なのでは? ふと頭によぎった。でも国境越えればフランス側でも有名なクリスマスマーケットはいくらでもあるし、その _vin chaud_(ホットワイン)やプレッツェルとか _choucroute_(ザワークラウト)なんかとも比べちゃう自分がいる。それぞれ独特だけど…ええと、思わぬ場面だった気もする。また脱線してしまった。でもまあ楽しかったから良し!
クリスマスマーケット巡り、本場ドイツ流はやっぱり一味違うかもね
ドイツがフランスよりも新しいアイデアに対して比較的開放的なのは、たぶんそのせいかもしれない。いや、違うかな……いや、でも実際そういう話をよく耳にするし。ちなみにっていうか余談だけど、これにはそこまで深い意味はないらしくて、ほとんどの国や都市がフランスより新しい考え方を受け入れやすいなんて皮肉っぽい意見もある。まあ、それはさておき。
うーん、それともハイデルベルクの場合、住民の25%が大学生という若者人口の多さが関係してるのだろうか、とふと思ったりする。なんで急にそんな話をしたんだっけ? ああ、元に戻すと、この町ではクリスマスマーケットにも影響が表れていて、伝統的なグリューワインだけじゃなくて――本当に見たことなかったんだけど――ホットテキーラとかまで用意されてたりする。不思議な感じだよね。それからベジタリアン向けプルドポークサンドイッチも見かけたなあ。
それに加えて、多くはないもののコオロギバーガーを売っている屋台もちらっとあった気がする。試す勇気は全然なかったけど。ま、いいか。また話逸れちゃった。でも結局、新しさへの受容度ってこういう小さなところにも現れるものなんだろうな、とぼんやり思った次第です。
うーん、それともハイデルベルクの場合、住民の25%が大学生という若者人口の多さが関係してるのだろうか、とふと思ったりする。なんで急にそんな話をしたんだっけ? ああ、元に戻すと、この町ではクリスマスマーケットにも影響が表れていて、伝統的なグリューワインだけじゃなくて――本当に見たことなかったんだけど――ホットテキーラとかまで用意されてたりする。不思議な感じだよね。それからベジタリアン向けプルドポークサンドイッチも見かけたなあ。
それに加えて、多くはないもののコオロギバーガーを売っている屋台もちらっとあった気がする。試す勇気は全然なかったけど。ま、いいか。また話逸れちゃった。でも結局、新しさへの受容度ってこういう小さなところにも現れるものなんだろうな、とぼんやり思った次第です。
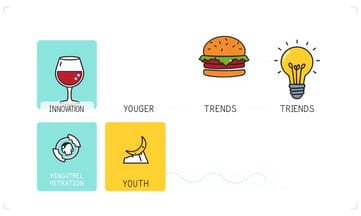
ホットテキーラにコオロギバーガー?若さが生むヘンテコ屋台列伝
ハイデルベルクには古い城があるんだよね、というかまあ「城」と言っても今は廃墟の雰囲気が強くて、なぜか僕はそういう壊れかけたものに惹かれる。いや、なんでなんだろう。ああ、話を戻そう。このハイデルベルク城だけど、長い歴史の中で2度ほど落雷に見舞われて部分的に損傷したことがある。ま、普通ならそれ自体が警鐘みたいな話にもなるんだけど——実はそれよりも本格的な破壊が起きたのは17世紀後半のこと。
その頃フランス軍がこの場所を占拠して、爆薬まで使って徹底的に壊したらしい。それにしても7メートルもの厚さを持つ火薬塔の壁、それすら卵の殻みたいに割れるなんて想像できる?うーん、自分だったら全然ピンとこない。でも現実としては、その塔の崩れた部分はいまでも残っている構造物にもたれかかるようになっちゃっていて、雨で黒ずみ苔むしているわけだ。変な話だけど時間のおかげで景色になった感じ。
あとさ、塔内には無事だった部屋も残っていてね。その部屋から背後の森林へ向けて開口してる様子を見ると、「意外と生き延びてる空間もあるんだな」って思えてくる。不思議と救われる気持ちになる瞬間もあるかな…ま、とりあえずそんなところかな。
その頃フランス軍がこの場所を占拠して、爆薬まで使って徹底的に壊したらしい。それにしても7メートルもの厚さを持つ火薬塔の壁、それすら卵の殻みたいに割れるなんて想像できる?うーん、自分だったら全然ピンとこない。でも現実としては、その塔の崩れた部分はいまでも残っている構造物にもたれかかるようになっちゃっていて、雨で黒ずみ苔むしているわけだ。変な話だけど時間のおかげで景色になった感じ。
あとさ、塔内には無事だった部屋も残っていてね。その部屋から背後の森林へ向けて開口してる様子を見ると、「意外と生き延びてる空間もあるんだな」って思えてくる。不思議と救われる気持ちになる瞬間もあるかな…ま、とりあえずそんなところかな。
二度も雷に撃たれ爆破された城、フランス軍の爪痕と崩れゆく塔
著者による写真。うーん、いや、本当はもうちょっと光が欲しかったけど、まあいいか。私たちは城の敷地を静かに歩いていたんだけど、そのとき細かな霧雨が突然強くなってきて、傘なんて持ってこなかった自分を少し呪う。バスがちょうど門に着いたらしく、観光グループがぞろぞろと降りてきた。「本当にみんな好きだよな」、とか思いながら見ていると、一斉に保存状態の良い部分へ駆け込んでいった。ああ、人波ってなんだか苦手。でも彼らも疲れ切った目つきで甲冑とか忘れ去られた貴族の肖像画をぼーっと眺めている姿を見ると、不思議と親近感すら湧く気がした。ただその間も外では雲が厚さを増していた。
誰が気にするだろうか?いや、自分でもふと思ったんだけど、「見るべきもの」だからみんな来るだけで、それはTripAdvisorや誰かのブログの記事リスト――そういう「義務感」を満たすためなのかな、と考えてしまう瞬間だった。牛乳や卵のような生活必需品みたいに、「チェック済」と頭の中でマークして次の商品棚へ…えっと、ごめん、急にスーパーを思い出した。でも本題に戻れば、この場所には現実とは別世界への窓口みたいな何か――そういう体験も隠れていることがあると思わない?
私は歴史について多少知識はあるつもりなんだけど、この地域――プファルツ選帝侯とか、「Worms(ヴォルムス)の司教」と呼ばれる人物については正直全然知らない。それなのになぜこうも惹かれるのかわからなくなる時もある。その司教こそこの城で最初に記録された所有者なんだけど、その名前……まるでファンタジー小説から抜け出した登場人物みたいじゃない?妄想しすぎかな。でも、そういうところにも旅の面白さって潜んでいる気がする。
誰が気にするだろうか?いや、自分でもふと思ったんだけど、「見るべきもの」だからみんな来るだけで、それはTripAdvisorや誰かのブログの記事リスト――そういう「義務感」を満たすためなのかな、と考えてしまう瞬間だった。牛乳や卵のような生活必需品みたいに、「チェック済」と頭の中でマークして次の商品棚へ…えっと、ごめん、急にスーパーを思い出した。でも本題に戻れば、この場所には現実とは別世界への窓口みたいな何か――そういう体験も隠れていることがあると思わない?
私は歴史について多少知識はあるつもりなんだけど、この地域――プファルツ選帝侯とか、「Worms(ヴォルムス)の司教」と呼ばれる人物については正直全然知らない。それなのになぜこうも惹かれるのかわからなくなる時もある。その司教こそこの城で最初に記録された所有者なんだけど、その名前……まるでファンタジー小説から抜け出した登場人物みたいじゃない?妄想しすぎかな。でも、そういうところにも旅の面白さって潜んでいる気がする。
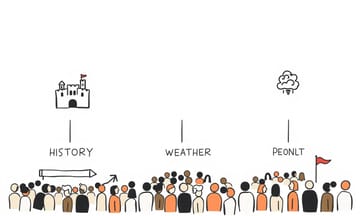
観光バスが吐き出す波、人混みをよそに雨と苔むす石段を歩く午後
どこか違う場所にいると、なんだか落ち着く——いや、「落ち着く」って言葉は少し違うかな、うーん、でもまあ、とにかく心地よいのだ。知らない町を歩いてると、新鮮さが身体の中をじわっと満たしていく気がする。あ、そういえば最近、事前に何も調べずにふらっと出かけることって減ったな…スマホで全部下調べしてしまってさ。気づけば、私たちはもう「新しい目」で世界を見るチャンスを自分からどんどん減らしてる。
写真や動画を1枚ずつめくりながら「ああ、ここも見た」「次はこれだ」みたいな感じで…ま、それも悪くはないけど。でも本当の体験――例えば月明かりの下でコロッセオが幽霊みたいに白く浮き上がる瞬間とか、夜空を背景に堂々とそびえるエッフェル塔の光――それは写真とは別物なんだよね。しかし、意外にも美しさって慣れちゃうものなのかもしれない。「またこの景色か」みたいな感覚になる自分がいて驚いたりもする。
最近ふと思ったんだけど(いや、本当にどうでもいい話なんだけど)、観光バスから降りてきた子供たちの顔を見ると、大人より感動が薄そうだったりして。それって現実世界――雨に濡れる木々とか12月の雨とか――そういうものよりも、スマホ越し・スクリーン越しに流れてくる絶え間ないドーパミン的な刺激のほうが勝っちゃう時代なのかなって思った。まあ…それでも現実世界はちゃんとそこにある。不思議なくらいね。
現実というものは雨みたいなものだ、とふと思う。一面の壁を埋め尽くす名前や顔――その持ち主たちはもう泥土へ消えてしまったし、その失われた時代――20世紀初頭の知識人階級による世界―すら今や幻影となった。しかしハイデルベルクだけは……いや、ごめん、一瞬脇道それてしまったけど、ともあれ、この街にはまだ別世界めいた空気が漂っているような気配がある。それだけは確かなことだと思いたい。
写真や動画を1枚ずつめくりながら「ああ、ここも見た」「次はこれだ」みたいな感じで…ま、それも悪くはないけど。でも本当の体験――例えば月明かりの下でコロッセオが幽霊みたいに白く浮き上がる瞬間とか、夜空を背景に堂々とそびえるエッフェル塔の光――それは写真とは別物なんだよね。しかし、意外にも美しさって慣れちゃうものなのかもしれない。「またこの景色か」みたいな感覚になる自分がいて驚いたりもする。
最近ふと思ったんだけど(いや、本当にどうでもいい話なんだけど)、観光バスから降りてきた子供たちの顔を見ると、大人より感動が薄そうだったりして。それって現実世界――雨に濡れる木々とか12月の雨とか――そういうものよりも、スマホ越し・スクリーン越しに流れてくる絶え間ないドーパミン的な刺激のほうが勝っちゃう時代なのかなって思った。まあ…それでも現実世界はちゃんとそこにある。不思議なくらいね。
現実というものは雨みたいなものだ、とふと思う。一面の壁を埋め尽くす名前や顔――その持ち主たちはもう泥土へ消えてしまったし、その失われた時代――20世紀初頭の知識人階級による世界―すら今や幻影となった。しかしハイデルベルクだけは……いや、ごめん、一瞬脇道それてしまったけど、ともあれ、この街にはまだ別世界めいた空気が漂っているような気配がある。それだけは確かなことだと思いたい。
予備知識ゼロで旅する心地よさ―スクリーン越しじゃない世界
自分の知っている場所と、特段大きな違いがあるわけでもなくてさ。ヨーロッパの他の都市と比較しても、そこまで異質だとは…いや、本当にそうなのか?うーん、自分でもよくわからない。でもまあ、クリスマスマーケットについては、何となく多くの場所より好印象を持った気がする。ああ、それにしても思いのほかアメリカ人が多かったな、と感じた瞬間もあった。
知らない土地にいるというだけで、不思議な魅力みたいなものを覚えることもあるんだよね。ま、いいか。でも結局、雨や寒さの中で歩き回りながらホットテキーラとかグリューワインを飲んで体を温めたり──その感覚こそ旅ならではじゃないかなと思ったりする。その後で待ってるキャンピングカーに戻るときの微妙な快適さ?うーん…それもまた悪くない、と今さら思い返す。
本当は計画なんてろくに立てず、その場その場で寄り道したり、自分が何にも知らない場所に紛れ込むこと、それ自体にこそ価値ってある気がする。だからロードトリップってやっぱ面白いし…ちょっと疲れるけどね。それでもまた行きたくなるから不思議だよ。
知らない土地にいるというだけで、不思議な魅力みたいなものを覚えることもあるんだよね。ま、いいか。でも結局、雨や寒さの中で歩き回りながらホットテキーラとかグリューワインを飲んで体を温めたり──その感覚こそ旅ならではじゃないかなと思ったりする。その後で待ってるキャンピングカーに戻るときの微妙な快適さ?うーん…それもまた悪くない、と今さら思い返す。
本当は計画なんてろくに立てず、その場その場で寄り道したり、自分が何にも知らない場所に紛れ込むこと、それ自体にこそ価値ってある気がする。だからロードトリップってやっぱ面白いし…ちょっと疲れるけどね。それでもまた行きたくなるから不思議だよ。


