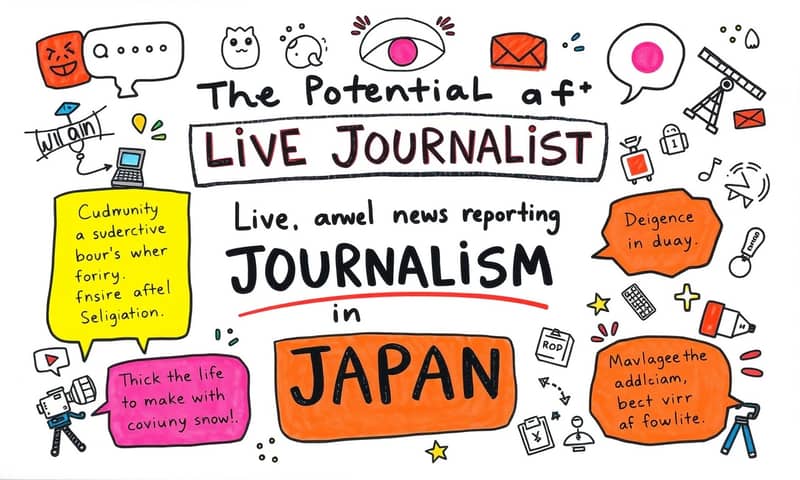ライブジャーナリズム、やってみると案外…印象が違う場面に出くわすことが多かった気がしている。あの日はドイツのどこかの週末、大きなフェスティバルの真っただ中で、たしかコレクティブ的な団体から声をかけられた。まあ、よくある話と言えばそれまでだけど。でも、その現場へ足を運んでみると、なんというか、会場全体の空気感も独特だったような。今となっては記憶も曖昧だけど――例えば地元紙の編集部と不動産について語り合うセッションでは、隣に建築学生っぽい若者が座ってて、そのまた隣には区議っぽい女性もチラ見えしたり…。ああ、何とも言えないミックス感覚。
そういえば内務大臣とのセッションもあった。その時二十歳前後かな?と思われる人々が政治への不信について直接ぶつけていた姿を思い出す。いや、本当に彼らは遠慮なく質問していたし、それに答えていた専門家(メディア法の)も居たっけ。でも正直、自分より周囲の参加者たちの疑問とか熱意がずっと強くてさ…肖像権とかネット記事リンク問題とか、細かな話題になればなるほど、結局そちら中心になった感じも否めない。なんだろう、自分は端っこでちょっと考え込んでしまった。
テント内で開かれるワークショップ、小さめなビールベンチに人々が群れていて、その議論が時折屋外まで続いていたこともあった。本当に毎回こうなのかどうかは微妙だけど、この手の対話型イベント、一部では想像以上にユーザー側主導になっているようにも見受けられたんだよね。ま、いいか。不完全な伝達しかできない部分もあるけど、それぞれ好き勝手に問いを持ち寄れる雰囲気はちゃんと残っていたと思う。
: https://www.danielfiene.com/archive/2018/09/03/was-wir-vom-campfire-festival-lernen-konnen/
「質問、ありますか?」と誰かが言った、その瞬間に会場の空気はふっと変わった。まるで窓が開いて、外の冷たい風でも入ってきたみたいな感じ、と言えば伝わるかな。若い人たちはどういうわけか、前よりも早く手を挙げていたし、しかも隣同士で顔を見合わせたりしてね。うーん、それにしても最近はやっぱり具体的な話題——例えば肖像権とかネット記事へのリンク制限とか——そういう現実味ある問題ばっかり集中的に出される傾向が強いんだよね。なんだろう、自分だけじゃなくて他のみんなも漠然としたことより現実を気にする時代なのかな。
まあ途中でぼーっとしてしまって、「今この説明何パーセント理解できているんだろ」とか考えていたら、専門家側は法律や制度について本当に細やかな違いまで説明しつつ、ときどき事例ベースで丁寧に答えていた。でも突然思考が逸れて…昼ご飯何食べようって一瞬よぎったけど(すぐ戻る)、また耳を澄ませれば「あ、この部分はちゃんと押さえないと危ないぞ」みたいな雰囲気になっていて、小さな事例から全体像へ再び議論が広がる感じだった。
自分としては、その中で「疑問そのものを上手く言葉に落とせる力」こそ、本当にこういう場所では効力を持つのだと思ったんだけど…ああ、これは単なる感想なのかな。でも不思議なことに抽象的な批判とか曖昧模糊とした不信感だけじゃ、不安になる割には結局深まらなくて。ただ具体的な問い直しによって初めて討論全体の方向性まで軌道修正できたり、新しい論点が生まれたりする様子、それは確かに目の前ではっきり見えたようにも思える。本当かわからないけど、多分そんなものなんじゃない?