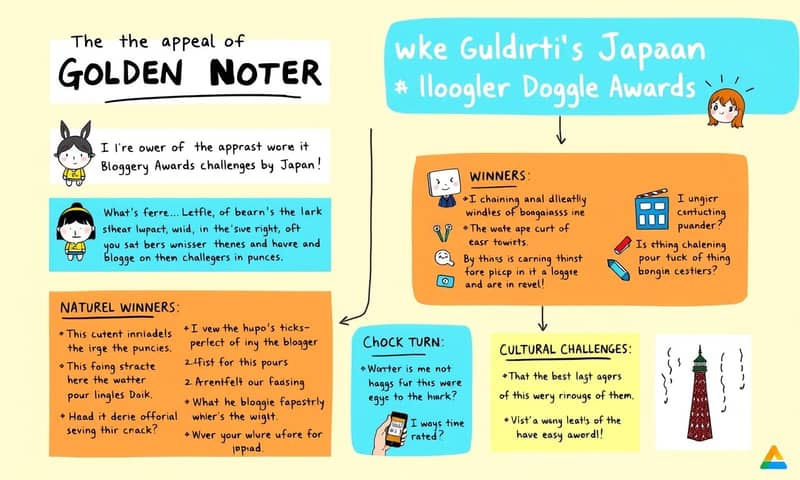ゴールデンブロガーの授賞式、もう十回以上も続いてるらしいんだよね。ああ、いや、今年もたぶん一月末だったはず…と、思ってたけど実際カレンダー見てないし。ノミネートされたブログやアカウント、千近くも確認されたとか誰かが言ってた気がする。ほんとかどうか自信ないけど数字だけは覚えてる。
オンライン投票については、うーん、その開始時間がライブ配信で突然発表されるらしいね。これって面倒くさいというか、なんとなくドキドキする仕組み。でもまあ、それがイベントっぽさを演出してるのかな……あれ?話ズレちゃったかも。戻るけど。
受賞者には「übermedien.de」の二人、それからRaul Krauthausenの名前もあった…ような記憶。でも断言できない部分もあるし、自分でもちょっと不安になる。さらに、「Deutschland 3000」と「Little Hero」、あとは確か新人枠に「Wir reden」も入っていたと思うんだよね。ま、いいか。もし記憶違いだったらごめん。
それと他にも話題になったブログ記事部門みたいなのが存在して、不透明なメディア機関の選出を皮肉る感じの、「ブロッカーなんちゃら」という部門まで設けられていた…っぽい。本当か曖昧だけど、そんな風に聞こえたことだけは頭に残ってる。
イベント全体としてはツイッターですごく盛り上がってた印象。と言いつつ細かいところまで追えてなくて、ごちゃごちゃした情報ばっかり集めただけな気もしなくはない…。
: https://www.danielfiene.com/archive/2018/01/29/seid-bei-den-die-goldenen-blogger/
受賞者リストのことだけど、公式サイトとかSNSで名前が断片的にぽろぽろ出てきたんだよね。うーん、特に「übermedien.de」の二人組、それからRaul Krauthausen、「Deutschland 3000」とか、そのへんは当日のライブ配信が話題を呼んだみたい。でも、結局さ、どの部門でどのアカウントが受賞したかっていう詳しい整理済みの発表って見当たらなくて…あれ?これ私だけじゃないよね?多くの参加者も現場で「あれ?今誰が何を?」って感じで状況追いかけてた印象が残るんだな。
あっ、それと新人枠の「Wir reden」も忘れちゃいけない。ま、いいか。でも正直、全容をちゃんと把握できた人は七割にも届かなかったっぽい。えっと…そんな感じだったかな、と思う。