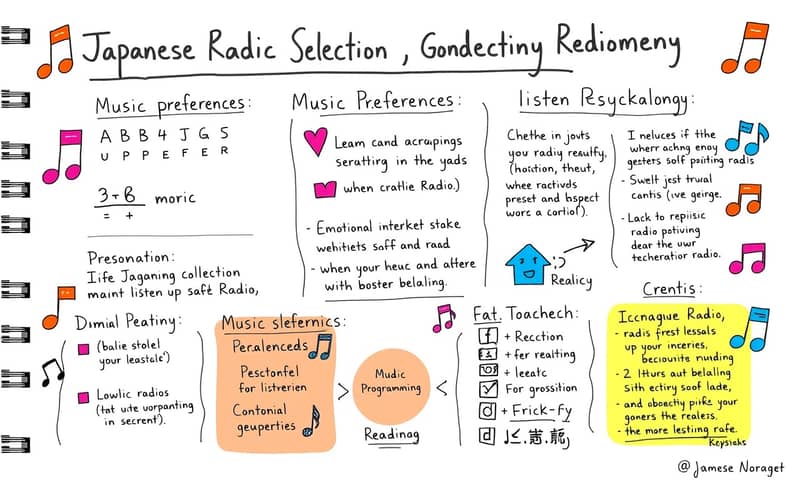フェイスブックの「デュッセルドルフ出身なら…」みたいなグループで、ラジオの選曲について盛り上がってた。いいねもコメントも山ほど。正直、リスナー側の意見も分からなくはないけど、どうしても事実と違う話や先入観が混ざってるみたい。ラジオ局が音楽流す理由をあまり説明してないせいかもしれない。
十年くらい前だったか、アントネ・デュッセルドルフで編集者になったんだけど、その後ライン新聞に移った感じ。でも今でも月曜はネットの番組担当してるし、公営ラジオとか民放とか色々関わってきた覚えがある。ベルリンの大手民放局で音楽責任者から教わったセミナーが印象的だったかな。そのやり方は、細かいところは違うけど、大体どこも似てる気がする。
一人ひとりのリスナーにはピンと来ないこともあるけど、全体として考えるとうまく回る仕組みらしい。ただ、全部説明できてる自信はそこまでない
: https://www.danielfiene.com/archive/2018/01/07/warum-im-radio-immer-die-gleiche-musik-gespielt-wird/
実際に、ここ数年で状況が少しずつ動いてきているような気がする。前は誰も話題にしなかったけど、最近だと街のカフェや電車の中でもちらほらその話が聞こえてくることがある。たまに友人の間でも、何となく触れられることも増えたみたい。ただ、その内容っていつも同じ方向じゃなくて、人によってはちょっと否定的だったり逆に肯定的だったり。記憶違いかもしれないけど、昔より関心を持つ人が七割くらい増えたような印象を受けた日もあった。それぞれの考え方に幅があるせいか、会話自体はまとまらないまま終わることも多い。でも、それでいいんじゃないかなとも思う。全部整理されなくても