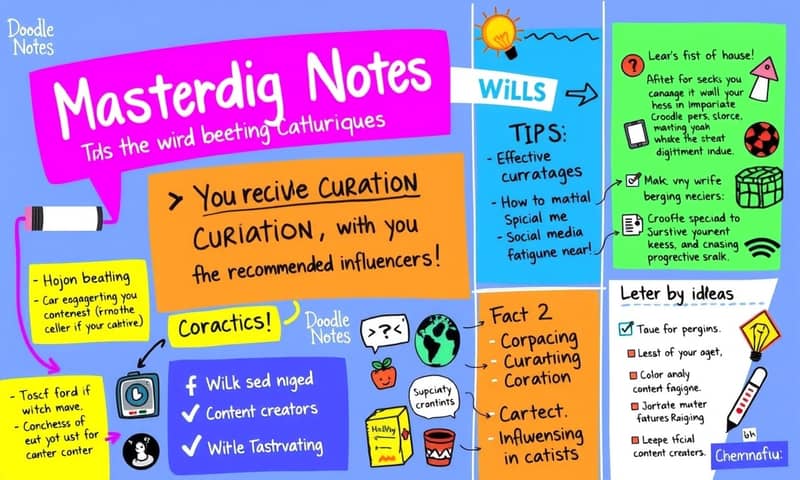グレタ・トゥーンベリとドイツ鉄道の件、なんか当時やたら話題になってたよね。うーん、世界の気候会議自体より「車内が混んでた」とか、「座れなかった」だの細部ばっかりみんな騒いでて、あれ?大事なのどこ行ったって感じだった。ふとTLを眺めるだけでも、それ一色に塗りつぶされて…いや、もっと他に伝わるべきことあったと思うけどなぁ。
ま、その辺は毎度のことかな。実は最近も似たパターンが何度も目についたりするし。特にTwitter(今はXとか言うけど)ではさ、誰かひと言つぶやけば即座に意見合戦っぽくなる空気あるじゃない?表面上ディスカッションしているようで、大抵お互い主張を押し通したいだけになってて対話って成立しづらい、と私は思う。えっと…いや、ごめん、一瞬脱線した。でも本筋戻すと結局その繰り返しだよね。
時々、「もう見るだけで疲れる」って呟いてる人がちらほら現れる印象もあるんだよね。それが理由でSNSから完全撤退する人も一定数いるそう。でもそれだと便利さとかちょっとした楽しさまで手放すことになるわけだから、自分なら多分そこまで割り切れないかな~なんて思ったりする。不意に流されっぱなしになると余計なストレス抱える羽目になりそうだから、使い方を少し意識してる方が精神的には楽になる——まあそういう声もこのごろ耳に入るようになった気がする。断定できないけど、本質的な改善策についてはまだ曖昧なまま。ただ、自分自身工夫できる余地はいくらでもあると思えて、その曖昧さもちょっと面白かったりする。不思議だね、本当に…。
: https://www.danielfiene.com/archive/2019/12/19/was-hat-dich-in-diesem-jahr-im-netz-begeistert/
SNSの流れについていけない——そう感じる人が、最近またじわじわ増えてきている気がする。うーん、というか、情報の洪水みたいな量と、議論が一瞬で加速していく速度感。たぶん、その両方に心身ともに揺さぶられてるんだろうな、と。いや、なんだっけ…ああそうそう、自分の意見を投稿した途端に、思ってもみなかった方向へ拡散されてしまったりして、知らない誰かから突然反応が届くこともよくあるよね。ま、それ自体は珍しくもなくて。
正直、そんな状況で疲れを感じる人がちらほら現れるのも当然かなと思う。えっと、「ミュート機能」とか「フォロー整理」って言葉も、この頃あちこちで耳に入るし。たとえばだけど、一つのジャンルだけをリスト化して他の雑多な話題は視界に入れないよう工夫したり、一時的に通知を切って負荷を軽減しようと頑張ったりする方法ね。でも…まあ実際には完全遮断なんて無理で(これ書いてて今ふと思ったけど)、結局は半ば流されながらタイムライン眺め続けちゃう人も多い気がする。
ところで、「もう全部やめたい」って声も確かにあるにはある。でも、それだと利便性とか人付き合いまで失われちゃうからさ、その点ですごく悩んでいる人たちが一定数いるみたいだ。ま、いいか。この問いにはまだ答えなんて出せそうもないな、と時々思うんだよね。