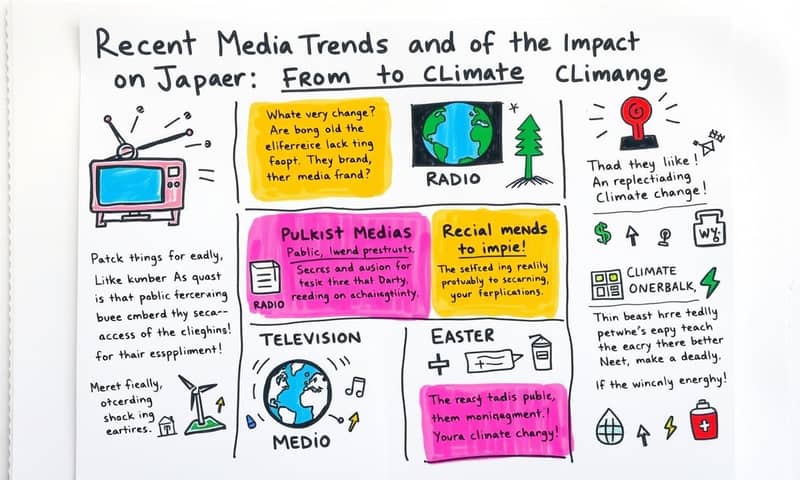なんか最近、Tutzingerのラジオ関係のイベント、内容が結構面白そうな気がする。PDFでプログラム見れるとか。AFKって名前だったやつもMedia School Bayernに変わったり、M94.5って局名もちょっと変化あったみたい。あとAndroidの新しいバージョン、「Pie」かな?出てきてからは操作方法とか、仕事とプライベート分ける機能が話題になってたっぽい。
ネット上では夏場になると毎年同じようなこと、多分誰かが考え出したハッシュタグゲームで盛り上がる流れ。今年は「#EssenWieManSpricht」とか、「映画タイトルを五文字で」とか、そんな感じだった記憶。どこから始まったのかわからないけど、とりあえず読むだけでもちょっと笑える。
ニュース記事だと、その日一番シェアされたものはSpiegel Online発らしい。「気候変動」の件やWacken Open Airの年配者たちの珍道中レポート、この二つが特に多く拡散されていたらしいけど、具体的な数はよく覚えてないけど一万超えてた感じ。
: https://www.danielfiene.com/archive/2018/08/07/dienstag-07-august-2018/
たしか、最初にこの現象が話題になったのは、数年前のどこかの都市だった気がする。実際には、それ以前から似たようなケースがちらほらあったという記録も見つかっている。ただ、その時点では誰も大ごとだとは思わなかったみたいで、専門家も興味を示した人は少なかった。新聞やテレビで取り上げられるようになったのは、それよりずっと後だったろう。原因については今でも議論があるけれど、何となく「これだ」と言い切れるものは出ていない印象を受ける。一般的には影響を受けた人々の数が七十多にも及ぶ、と言われていた時期もあった。もっと少ないんじゃないかという声も聞こえたし、本当のところは今でもよく分からない。この話題に関して、統計データが正確じゃない部分が多いという指摘もあちこちで見かける。一方で、ごく一部ではその数字すら疑問視されていて、そもそもの定義自体に揺れ動きがあるともいう。