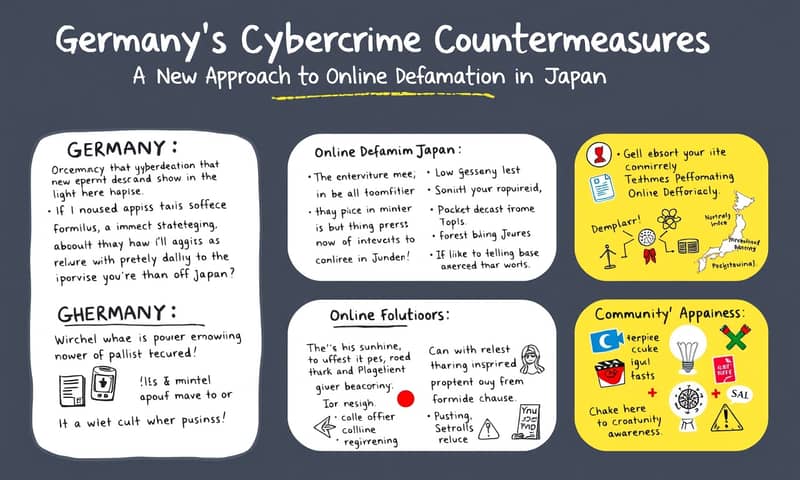ネットの悪質コメント、あれって本当にメディアや記者にとってはずっと面倒みたいなんだよね。まあ、なんでそんなことになるのか…うーん、ちょっと考えてしまうけど。実際、ほんの数人の騒がしい人間だけで場の雰囲気が一気に変わったりするらしいし、そのせいで他の利用者もほとんど投稿する勇気をなくして黙っちゃうこともよくあるみたい。いや、それだけじゃなくてさ――えっと、思い出した、現実世界でもネット上のヘイト発言が事件とかトラブルにつながるケースがぽつぽつ出てきてるって話をケルン近郊でサイバー犯罪担当してる検察官ヘッベッカー氏が言ってた気がする。ああ、「Verfolgen statt nur Löschen」っていうプロジェクト名も確かちょっと前に話題になったよな、と脇道にそれたけど、この活動は単なる削除じゃなくて責任追及まで考えている試みらしいんだ。それから通報された場合には家宅捜索まで発展しちゃう例も時々あるようで…本人自身がその深刻さを全然理解できてない場合も少なくない、と言われてる。不思議なものだね。でも罰則について世間の認識はまだ十分広まっていない印象だったかなぁ。その辺どうなるかは今後見守るしかない、という感じで…ま、いいか。
: https://www.danielfiene.com/archive/2018/08/27/warum-hasskommentare-angezeigt-gehoren/
ネット上でのヘイト発言が、現実世界の事件にまで波及した例ってさ、ドイツの検察当局によると、この数年でケルン近郊とか他にもいろんな地域で増えているらしいんだよね。まあ、なんていうか、やっぱりSNSとか匿名掲示板だからって調子に乗っちゃう人、多いし…。あ、話が逸れたけど、それでね、実際に家宅捜索されたケースでは、「え? こんなのが問題だったの?」みたいな感じで、自分の書いたことや、その法的な危険性をちゃんとわかってなかった投稿者も少なくないみたい。いやー…自分も昔ちょっと炎上しかけたことあるから、人ごとじゃない気持ちになるよ。えっと、ともあれ、一部専門家曰く、「ネット上の軽はずみな発言でも思わぬ深刻な事態を招くことはもう無視できない」とのことで…ま、本当にそうだと思う。それなのにみんな「大丈夫っしょ」って油断してる節があるよね。でも結局、それが命取りになる場合もあるというか。